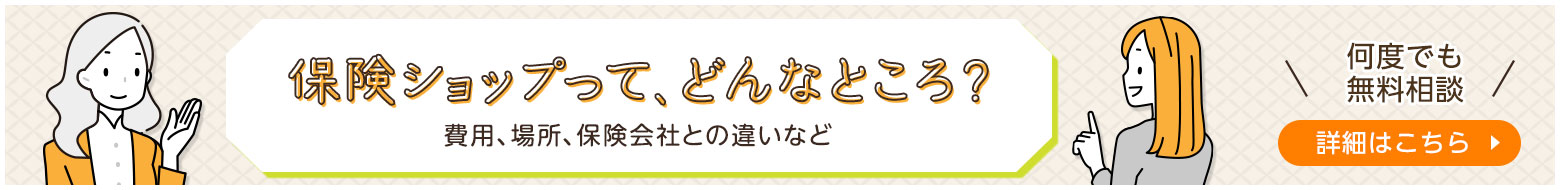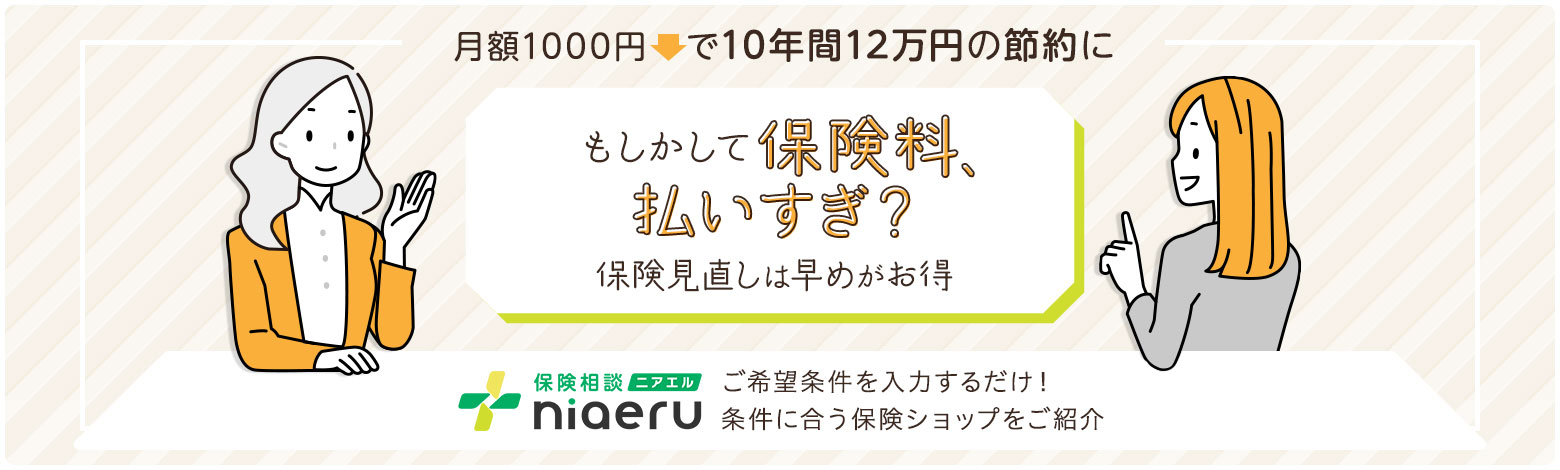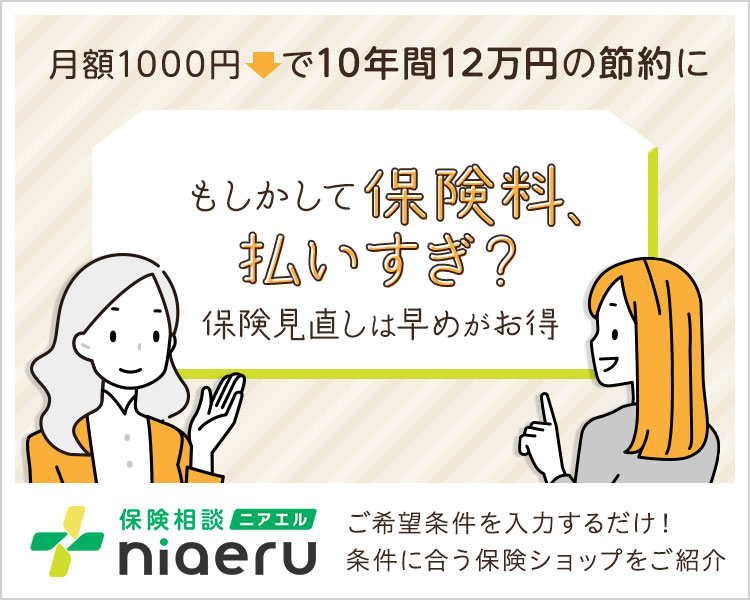「がん」「心疾患」「脳血管疾患」は「三大疾病」と呼ばれ、50歳代から70歳代ではこの3つで死因の50%超を占めています。死につながるだけでなく、三大疾病にかかると治療が長期に渡り、経済的負担が大きくなることも少なくありません。今回は、三大疾病に罹患するとどんなリスクがあるのか、どういった生命保険で備えておけばよいのかを解説します。
「がん」「心疾患」「脳血管疾患」は「三大疾病」と呼ばれ、50歳代から70歳代ではこの3つで死因の50%超を占めています。死につながるだけでなく、三大疾病にかかると治療が長期に渡り、経済的負担が大きくなることも少なくありません。今回は、三大疾病に罹患するとどんなリスクがあるのか、どういった生命保険で備えておけばよいのかを解説します。
目次
1.三大疾病とは「がん」「心疾患」「脳血管疾患」の3つ
三大疾病とは、「がん(悪性新生物)」「心疾患」「脳血管疾患」のことを指します。厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計」によると、三大疾病が日本人の主な死因の1位、2位、4位を占めています。
| 死因順位 | 死因 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | がん(悪性新生物) | 24.3% |
| 2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 14.7% |
| 3位 | 老衰 | 12.1% |
| 4位 | 脳血管疾患 | 6.6% |
| 5位 | 肺炎 | 4.8% |
出典:「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」/厚生労働省
入院・通院患者数で見ても、三大疾病の脅威がわかります。特に入院患者数では、4分の1近くが三大疾病による入院であることがわかります。このことから、いかに多くの人が三大疾病の病魔に侵されているかということがわかります。
| 疾病分類 | 入院患者数(割合) | 外来患者数(割合) |
|---|---|---|
| 総数 | 117万5300人(100%) | 727万5000人(100%) |
| がん(悪性新生物) | 10万6100人(9.0%) | 18万6400人(2.5%) |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 5万7200人(4.8%) | 13万9000人(1.9%) |
| 脳血管疾患 | 10万9400人(9.3%) | 7万4800人(1.0%) |
出典:「令和5年(2023)患者調査の概況 」/厚生労働省
続いて、それぞれの病気について詳しく見ていきましょう。
1-1.がん(悪性新生物・上皮内新生物)
がんは、異常な細胞(がん細胞)が体内で増殖する病気です。がんの種類は、「悪性新生物」と「上皮内新生物」があります。悪性新生物は、がん細胞が基底膜を超えて広がる浸潤や転移の可能性がある状態を指します。
一方、上皮内新生物はがん細胞が上皮部分に留まり、浸潤や転移の可能性が非常に少ない状態です。三大疾病のひとつ、いわゆるがんに該当するのは「悪性新生物」で、日本人の死因第1位となっています。主な治療法は手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤)がいままで三大治療と呼ばれてきましたが、最近はこれに免疫療法が加わって4大治療とも呼ばれています。一般的な病気は、手術をすればあとは治癒を待って完治、ということが多いです。しかし、ガンの場合、転移&再発のリスクが高いため、手術をしたとしても、しなくとも、放射線療法や化学療法を組み合わせて、平均しても4~5年は治療を続けます。そのため、治療費が長期にわたってかかることになります。
1-2.心疾患
何らかの原因によって心臓に異常が起こり、血液の循環が滞って起こる病気を心疾患といいます。
代表的な病気は、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)や不整脈、心臓弁膜症、心不全があります。心疾患は日本人の死因第2位となっており、とくに虚血性心疾患は重症化して命に関わることもあるため、早期発見・治療が大切です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病や喫煙が原因となっていることが多いといわれています。
1-3.脳血管疾患
脳血管疾患は、脳の血管トラブルによって発症する病気の総称です。
代表的な病気は、脳卒中と呼ばれる脳出血、くも膜下出血、脳梗塞があります。主な治療法は血栓溶解術や血管内治療、手術などで、治療が遅れると重篤な後遺症が残ったり命に関わったりすることがあります。傷病別の平均入院(在院)日数で見てみると、総合失調症、気分(感情)障害、アルツハイマー病などを除くと、もっとも期間が長いのが、この疾病となっています。
2.三大疾病にかかった際のリスク 三大疾病にかかった場合、以下のようなリスクが考えられます。
三大疾病にかかった場合、以下のようなリスクが考えられます。
2-1.医療費が高額になる可能性
厚生労働省「医療給付実態調査(令和3年度)」によると、三大疾病の入院・入院外にかかる医療費は以下の通りです。
| 疾病分類 | 入院 | 入院外 |
|---|---|---|
| がん(悪性新生物) | 77万4,890円 | 6万7,397円 |
| 虚血性心疾患 | 82万3,103円 | 1万6,150円 |
| 脳血管疾患 | 82万9,028円 | 1万6,053円 |
出典:医療給付実態調査 報告書 令和3年度/厚生労働省
※協会(一般)・組合健保・共済組合・国民健康保険計・後期高齢者医療の合計より平均金額を算出
上記の医療費は公的医療保険適用前の金額であるため、年齢や所得に応じて1〜3割の負担となります。自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給される高額療養費制度が適用されます。
しかし、入院時の差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料など、公的医療保険の適用外の費用は自己負担です。長期的な治療が必要となったり、先進医療を受けたりする場合は、医療費が高額になる可能性があります。特にがんの場合は、入院・手術で治療が終了ではなく、このあと、数年にわたる通院での治療費負担があります。たとえば、5年間の入院治療費は200万円とも300万円ともいわれています。
2-2.治療期間が長くなる可能性
厚生労働省の「令和5年(2023)患者調査の概況」によると、三大疾病の入院時の平均在院日数は以下の通りです。
<三大疾病の平均在院日数>
| がん(悪性新生物) | 14.4日 |
|---|---|
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 18.3日 |
| 脳血管疾患 | 68.9日 |
上記は入院日数ですが、脳血管疾患の入院期間の長さが目立ちます。しかし、三大疾病の場合、退院後も薬物治療などさまざまな治療が継続することが多いです。体力や機能を回復するリハビリも重要となるため、治療期間が長期にわたる場合があります。
2-3.仕事できず休業・休職したり、退職する可能性
三大疾病にかかると、入院や通院、薬の副作用や後遺症によって日常生活に支障が出る場合が少なくありません。そのため、今までのように仕事ができなくなり、収入が減ってしまう可能性もあるでしょう。実際、がん診断後の就労への影響調査をみると、休職・休業はしたが、退職・廃業はしなかった人が54.2%、退職・廃業した人が19.8%という結果も出ています(「平成30年患者体験調査報告書」国立がん研究センターがん対策情報センター)。治療の負担が仕事にも影響し、ひいては収入減や仕事そのものを失ってしまうことにもつながっていることがわかります。
2-4.介護が必要になる可能性
厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、要介護状態になる主な原因の2位は「脳血管疾患(脳卒中)」となっています。
<要介護者等の介護が必要となった主な原因>
| 1位 | 認知症 | 16.6% |
| 2位 | 脳血管疾患(脳卒中) | 16.1% |
| 3位 | 骨折・転倒 | 13.9% |
「心疾患」は 5.1%、「がん(悪性新生物)」 は2.7%を占めており、三大疾病にかかると後遺症が残ったり寝たきりになったりして介護が必要となるリスクがあります。医療費以外にも介護費用がかかったり、介護する家族の収入が減ったりして、経済的負担が大きくなる可能性があるでしょう。
3.リスクに備えられる三大疾病保険
ここでは、リスクに備えられる三大疾病保険の保障内容や期間、条件、特約、がん保険との違いについて紹介します。
3-1保障内容
三大疾病保険は、「がん」「心疾患」「脳血管疾患」の三大疾病によって、保険会社が定める所定の状態になった場合に一時金を受け取れる保険です。三大疾病保険の保障に加えて、死亡または高度障害状態になった場合、介護状態・身体障害状態になった場合などに保険金を受け取れる商品もあります。
3-2.保障期間
三大疾病保険の保険期間は、「終身型」と「定期型」があります。終身型は保障が一生涯続く保険で、死亡保障が付いている商品は途中解約した場合は解約返戻金が受け取れることが多いです。
定期型は一定期間保障される保険で、掛け捨てタイプが一般的です。
3-3.保険の保障を受けられる条件
三大疾病保険の保障を受けられる条件は、商品の保険内容によって異なります。例えば、死亡保障付きの三大疾病保険の場合、以下のような条件を満たしたときに保険金が支払われるのが一般的です。
①がん
・初めてがんにかかったと医師によって診断されたとき(上皮内新生物・皮膚がんは除く)
②心疾患
・急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上労働制限が必要とされる状態が継続したと医師によって診断されたとき
・急性心筋梗塞の治療を目的とした手術を受けたとき
③脳血管疾患
・脳卒中(脳出血・くも膜下出血・脳梗塞)を発病し、初診日から60日以上言語障害や運動失調、まひなどの後遺症が継続したと医師に診断されたとき
・脳卒中の治療を目的とした手術を受けたとき
④高度障害状態
・傷害や疾病によって所定の高度障害状態になったとき
⑤死亡
・死亡したとき
3-4.三大疾病保険の特約
三大疾病保険の特約には、以下のようなものがあります。
<リビング・ニーズ特約>
余命6ヶ月と医師に診断された場合、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。生前給付金として受け取ると死亡保険金はなくなり、保険契約が終了となります。リビング・ニーズ特約には保険料がかかりません。
<保険料払込免除特約>
保険会社が定める三大疾病の所定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除される特約です。
3-5.がん保険との違い
がん保険は、三大疾病のひとつである「がん」に備える保険です。保険商品によって異なりますが、がんと診断されたときの一時金、通院、入院、手術時の給付金、所定の治療を受けた際の月ごとの給付金などを受け取れます。がんに特化した保険なので、心疾患・脳血管疾患など他の病気に対する保障はありません。三大疾病保険よりも保険料を抑えられるメリットがありますが、ひとつの保険で幅広く備えたいときは三大疾病保険が良いでしょう。
4.三大疾病保険に加入するときの注意点

保険会社によって保険内容は異なるため、三大疾病保険に加入するときは以下の点を確認しておきましょう。
4-1.支払い条件
三大疾病保険は、がんは悪性新生物のみ、心疾患は急性心筋梗塞のみ、脳血管疾患は脳卒中のみが対象となっているのが一般的です。保障範囲が広いものもあるので、どのような病気が対象となるのか確認しましょう。また、保障を受けるには保険会社が定めた条件を満たす必要があるため、病気の種類ごとの支払い条件を確認しておくことも大切です。
4-2.給付回数
三代疾病保険の保険金を受け取れる回数は1回が一般的ですが、複数回受け取れるタイプや無制限タイプもあります。複数回や無制限に受け取れる場合でも「1年に1回のみ」といったような条件が設けられていることもあるので、給付回数や条件を確認しておきましょう。
4-2.免責期間
三大疾病のうち、がんの保障は契約後90日間または3ヶ月間の免責期間が設けられていることがあります。免責期間中は、がんと診断されても給付金を受け取れないので注意が必要です。
三大疾病に備え自分に合う保険を見つけよう!
三大疾病にかかると、長期的な入院や通院、高額な医療費、収入の減少などのリスクがあります。三大疾病は日本人にとって身近な病気のため、健康なときに備えておくことが大切です。三大疾病にかかったときの経済的なリスクに備えることができるのが、「三大疾病保険」です。保険会社によって保険内容や支払い条件、給付回数などが異なるため、自分に合う保険を見つけましょう。
保険ショップの予約はこちら
1分で完了! 当日・翌日もOK!
予約・相談無料お電話でも予約可能!
通話無料・年中無休|受付/9:30~18:30
保険ショップの予約はこちら
まとめ
・三大疾病とは「がん」「心疾患」「脳血管疾患」のこと
・三大疾病にかかると「医療費が高額になる」「治療期間が長くなる」「仕事ができずに収入が減少する」「介護が必要になる」といったリスクがある
・三大疾病保険に加入する際は、支払い条件・給付回数・免責期間を確認することが大切