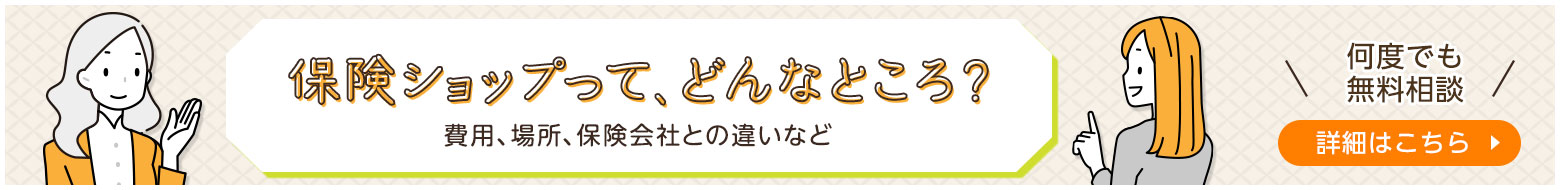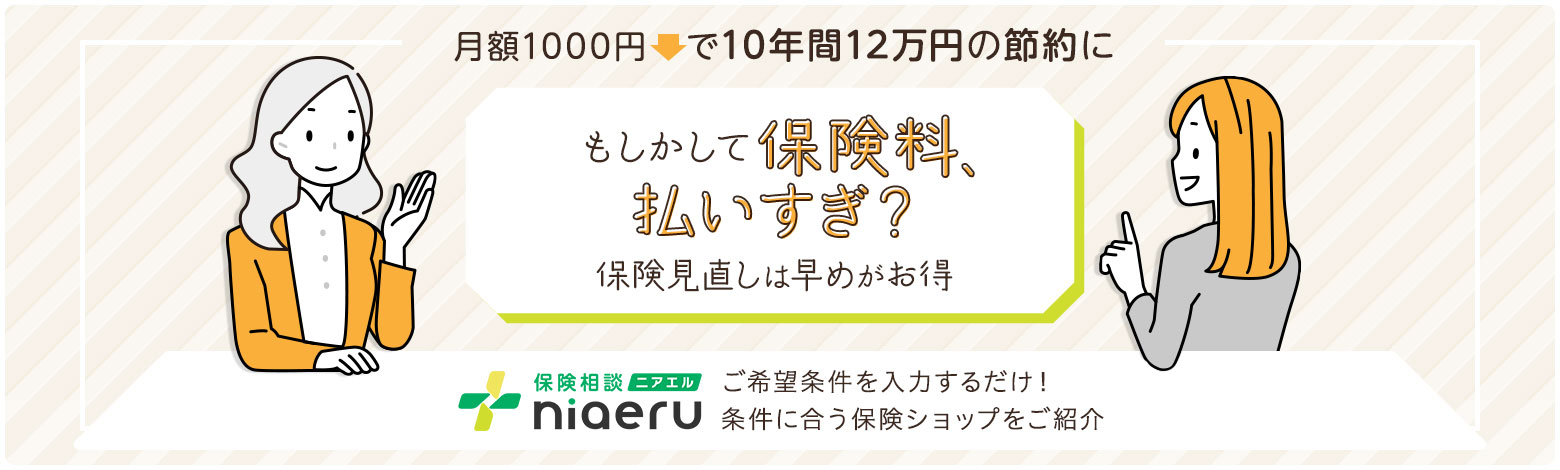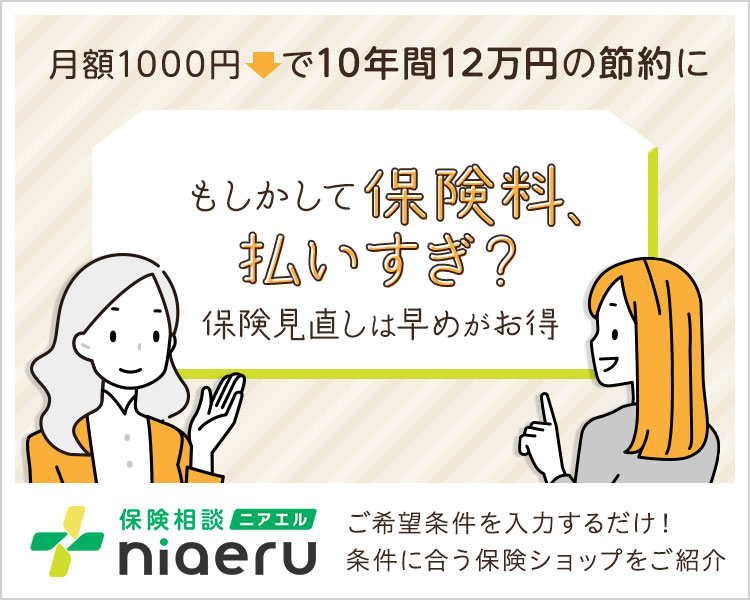子どもの教育資金を確保するため、学資保険に加入する方は多いですが、その学資保険には税金が大きく関係していることをご存知ですか?学資保険について正しく理解すれば、節税効果を最大限に引き出し、より多くの教育資金を確保できます。この記事では、学資保険を活用した節税方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
プロの保険相談なら、取扱保険会社数の多い保険ショップがおすすめです。目次
学資保険は保険料控除の対象か?
「学資保険の保険料って、税金と関係あるの?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。実は、学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、生命保険に加入している場合、支払った保険料に応じて所得税と住民税が減額される制度です。
学資保険は、生命保険料控除の中でも一般生命保険料控除に該当します。つまり、学資保険に加入することで、税金を安く抑えることができるのです。
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除があります。学資保険は、この中の一般生命保険料控除に含まれており、学資保険に加入していると税金を安く抑えることができます。ただし、控除には限度額が設定されているので、支払った保険料の全額が控除されるわけではありません。
学資保険料の控除を申請する時の注意点
学資保険料の控除を申請する際は、契約した時期によって控除額が異なる点に注意が必要です。生命保険料控除は契約した時期によって旧制度と新制度に分けられ、控除額が異なります。
- 平成23年12月31日以前の契約: 旧制度が適用され、一般生命保険料控除の限度額は5万円
- 平成24年1月1日以降の契約: 新制度が適用され、一般生命保険料控除の限度額は4万円
さらに、他の生命保険や個人年金保険などに加入している場合、控除限度額を超えてしまう可能性もあります。
学資保険で保険料控除を受ける方法は?
では実際に、学資保険料の控除はどのように受ければいいのでしょうか?学資保険料の控除を受けるためには、控除の手続きを行う必要があります。会社員と個人事業主では手続きが異なりますので、それぞれの手順を説明します。
会社員が学資保険控除を受ける場合は「年末調整」
会社員の場合は、勤務先の「年末調整」で学資保険料控除の手続きを行います。勤務先から渡される「給料所得者の保険料控除等申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して会社に提出すれば、手続きは完了です。「生命保険料控除証明書」は、毎年10月頃に保険会社から送られてきます。申請の際は必ず必要になりますが、紛失してしまった場合でも再発行してもらえます。
個人事業主が学資保険控除を受ける場合は「確定申告」
個人事業主の場合は、「確定申告」によって学資保険料控除の手続きをします。確定申告書に控除額を記入し、税務署に提出すれば申請は完了です。年末調整と同様、「生命保険料控除証明書」が必要になります。
学資保険を受け取る時に税金がかかる?
学資保険を受け取る時、税金が発生する場合があります。学資保険は、受け取り方や受取人によって税額が異なるので、注意が必要です。
学資保険を満期金として一括で受け取る場合と分割で受け取る場合の違い
学資保険が満期になると、満期金として受け取ることができます。満期金は、一括で受け取る方法と分割で受け取る方法があります。
- 満期金を一括で受け取った場合: 一時所得として扱われます。一時所得とは非営利目的で生じた一時的な所得のことで、課税対象ですが50万円分の特別控除があります。一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得=(満期保険金−支払った保険料)−特別控除50万円
現在は、学資保険の満期保険金から支払った保険料を引いた額が特別控除額の50万円を大きく超えることは少ないため、課税されることはほぼないと考えてよいでしょう。満期金を一括で受け取る場合、税金を納めることはほとんどありません。
- 満期金を分割で受け取った場合: 雑所得として扱われます。満期金を分割で受け取る場合は、学資年金と呼ぶこともあります。雑所得も一時所得と同様に所得税に含まれますが、一時所得のような特別控除がありません。雑所得は、以下の計算式で算出されます。
雑所得=学資年金額−(学資年金額×払込保険料総額÷総支給見込額)
雑所得は特別控除がないため、ほとんどのケースで税金が発生します。契約者が会社員の場合は、他に合算する雑所得がなければ20万円までは非課税になりますが、一括で受け取った場合よりも税金がかかる可能性は高いです。また個人事業主の場合は20万円の非課税枠もないため、学資保険の満期金はできるだけ一括で受け取るべきです。
学資保険を受け取るのが契約者以外の場合
学資保険の満期金の受取人も、税金に関係します。受取人が契約者以外の場合は、贈与として扱われ、贈与税の課税対象になります。贈与税は、受け取った満期金から贈与税の基礎控除額110万円を引いた金額が課税対象額になります。学資保険の満期金は、ほとんどの場合110万円を大きく超えるため、税負担が大きくなってしまいます。したがって、満期金を受け取る場合は「契約者本人」が「一括」で受け取るのがベストでしょう。
まとめ:満期時に税金がかからないように注意!
税金を考慮しないで学資保険に加入するのは危険です。学資保険で税金をできるだけ抑えるために、控除制度を活用し、満期金は契約者本人が一括で受け取るようにしましょう。学資保険の仕組みとそれに関係する税制を正しく理解して、税金を最小限に抑えるようにしましょう。
実際に保険を選ぶのは非常に難しいため、プロの意見を聞くのも良い選択です。保険相談なら、取扱保険会社数の多い保険ショップがおすすめです。