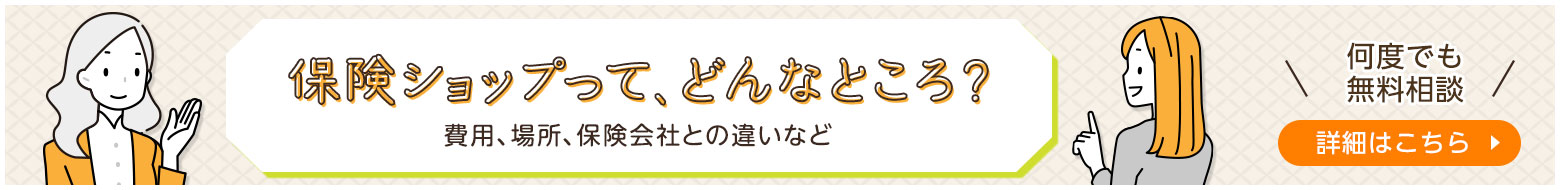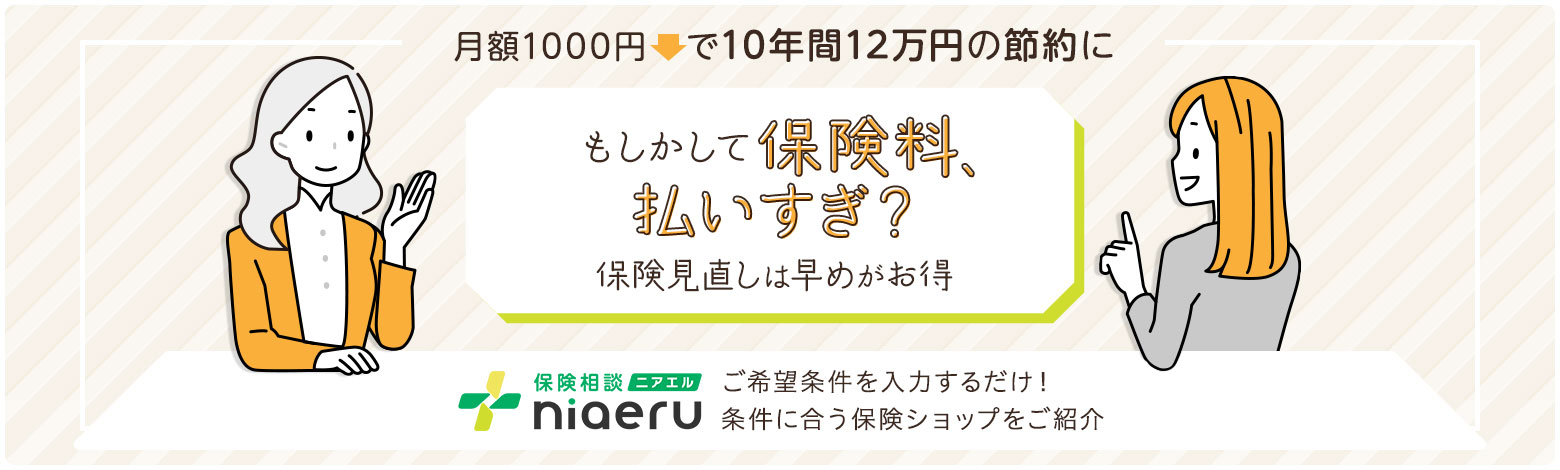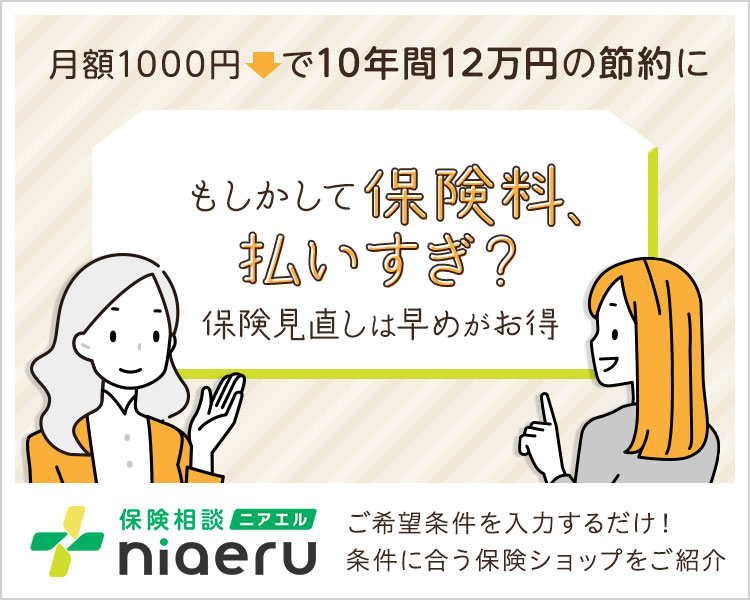目次
確定申告について
生命保険に関連する控除には、生命保険料控除と医療費控除があります。これらの控除を受けるための方法についてみていきましょう。
生命保険料控除
生命保険料を支払っている人は、一定の金額まで生命保険料控除を受けられ、税金額が少なくなります。会社員や公務員などの給与所得者は、職場に生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出すれば、年末調整で払いすぎた税金が戻ってきます。また、証明書の提出を忘れたりして、年末調整での控除が受けられなかった場合でも、確定申告によって申請ができます。確定申告の義務のない給与所得者は、過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。自営業やフリーランスの人は、所得税の確定申告をする際に「生命保険料控除証明書」を添付することで保険料控除の申告をすることができます。
医療費控除
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の自己負担額が、10万円(または所得金額の5%)を超える場合は、200万円を限度に医療費控除を受けられ、税金額が少なくなります。医療費には、本人分だけでなく、生計を同一にする配偶者やその他の親族(両親や子供など)の分も含めることができます。
| 医療費控除額(限度:200万円)=支払った医療費-保険などで補てんされる金額-10万円(または所得金額の5%) |
生命保険や医療保険などから、医療費の補てんとなる給付があった場合は、給付を受け取った人の医療費から差し引きます。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の義務のない給与所得者の場合は、過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。医療費控除の対象となるものには、健康保険が使えるものだけでなく、市販薬や病院への交通費も含まれます。家族が多い場合などは、合算すると医療費控除の対象となる可能性があるので、病院や薬局の領収書をとっておき、年末に確認するとよいでしょう。
| ・病院での治療費 ・歯科での治療費(インプラントも対象) ・治療のために購入した薬の代金(市販薬も対象) ・病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車・バスなど) ・けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用 ・入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料 ・助産師が分娩の介助をした場合の介助費用 ・介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額 ・人間ドッグや検診費(異常が見つかって治療した場合) |