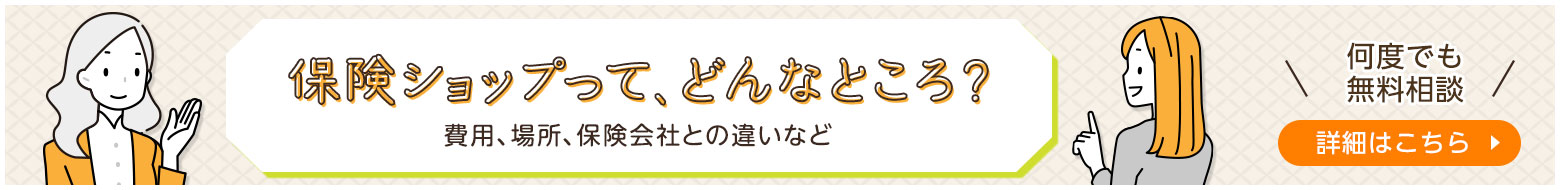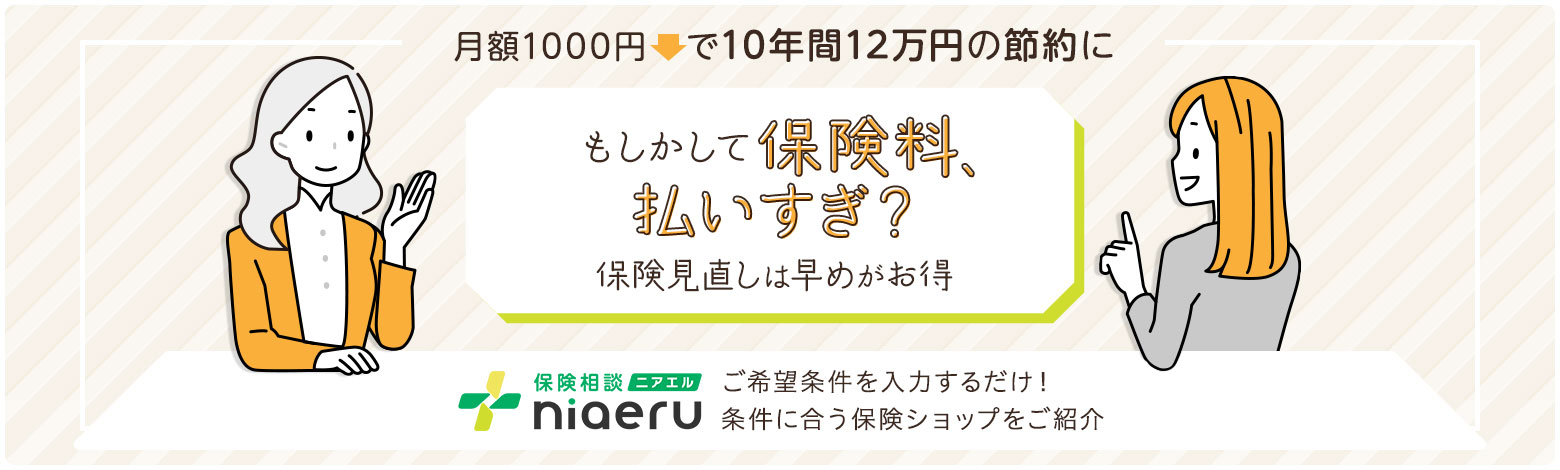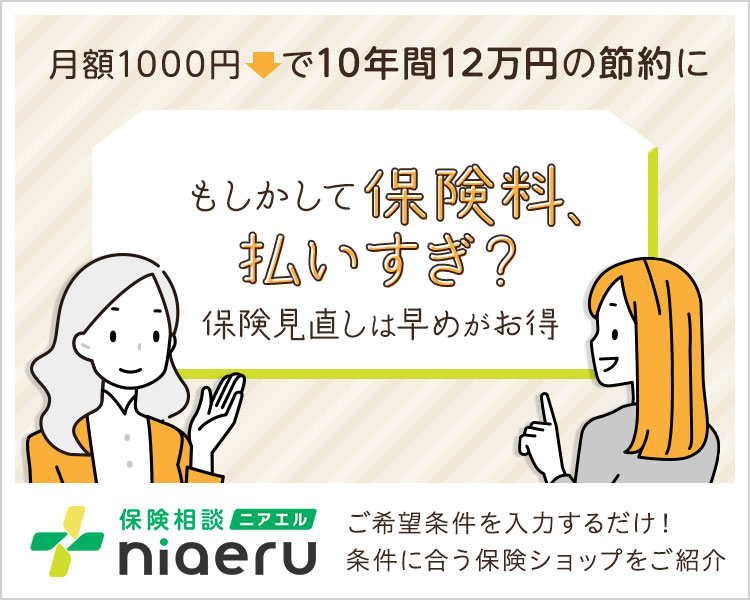こどもが産まれたばかりの家庭は、最もリスクが大きい状態にあると言っても過言ではないでしょう。なぜなら、こどもが独立するまでには日々の生活費だけでなく、教育費をはじめとした、まとまったお金がかかるからです。
リスクの種類は主に以下の4つがありますので、まずはそれぞれについて理解してください。
目次
こどもが産まれたばかりの家庭にはどんなリスクがある?
死亡のリスク
家計を支える世帯主に万が一のことがあると、残された配偶者やこどもの生活費・教育費が不足するリスクがあります。一定の条件を満たせば国から遺族年金を受け取ることもできますが、決して十分な金額とは言えないため、保険を活用してしっかりと備えることが必要になります。
また、死亡すれば葬儀費用がかかりますし、お墓がなければその費用も必要になります。こうした備えも必要です。
病気やケガのリスク
世帯主・配偶者・こどものいずれも病気やケガをするリスクがあります。入院したときの医療費はもちろん、通院で治療することが増えたがんの医療費、さらに生活習慣病も想定して備えておくことが望ましいでしょう。
なお、医療費の備えを考える上では健康保険の「高額療養費制度」や「傷病手当金」について知っておくことが大事です。また、こどもの医療費については自治体からの助成があるため、健康保険が使える治療であれば実質負担がほとんどないでしょう。
働けないリスク
大きな病気やケガが原因でそれまでと同じように働くことができず、収入が減ってしまうリスクもあります。所定の条件を満たせば国から障害年金を受け取ることができますが、その金額は生活する上で決して十分とは言えません。こうしたリスクは保険で備えることができます。
介護のリスク
若い世代でも交通事故などが原因で、要介護状態になるリスクはあります。ただ、確率はそれほど高くありませんし、生命保険会社が取り扱う介護保険で備えることもやや難しいと考えられます。こどもが産まれたばかりの家庭であれば、介護のリスクより働けないリスクに備えることを優先させることをおすすめします。
将来に向けて準備したほうがよいお金とは?
こどもが産まれたばかりの世帯にとって、将来のために準備しておくべきお金は以下の3つです。
| 教育資金 | 大学進学に向けての準備を。私立・公立で大きく変わる。 |
|---|---|
| 住宅資金 | 住宅ローンの頭金を考えるには期間が短い可能性が大。繰り上げ返済に向けた準備を。 |
| 老後資金 | 個人年金保険料控除等を活用し、無理のない範囲で。 |
教育資金
日本政策金融公庫が発表した「教育費負担の実態調査結果」(平成31年度)によると、高校卒業後、大学の入学費用と在学費用を合計した金額は、国公立で539万3000円、私立文系で730万8000円、私立理系で826万7000円という結果が出ています。
つまり、4年制大学なら卒業までにおおよそ500万~900万円程度を準備する必要があるということです。私立中学や私立高校に入学すればさらにお金がかかるので、よりしっかりと備えることが必要になります。
住宅資金
マイホームを購入する場合は教育資金の負担に加え、頭金やローン返済のための資金を確保しなければなりません。老後に住宅ローンを残さないようにするためには教育資金と同様に、計画的な準備をすることが大切です。
老後資金
教育資金や住宅資金の準備に精一杯で、老後の資金作りまで手が回らないという家庭も多いかもしれません。しかし、若いうちから準備すれば時間を活かすことができ、かつ選択肢が多くなるというメリットがあります。優先順位としては他の2つよりも低いですが、余裕ができたら少しずつ準備することをおすすめします。
想定されるリスクに保険で備える方法
以上で解説してきたリスクについて、保険で備える場合はどのようにしたら良いのでしょうか。ここでは世帯主・配偶者・こどものそれぞれに分けて解説します。
世帯主のリスク
こどものいる家庭は、家計を支える世帯主のリスクがとても大きいです。どんなリスクがあるのかを正しく把握してしっかりと備えましょう。
| リスク | 子供が生まれたとき | 保険の種類 |
|---|---|---|
| ①死亡のリスク | 自己の葬祭費用 家族の生活費用 家族の住居費用 子供の教育費用 |
定期保険 終身保険 収入保障保険 |
| ②病気・ケガのリスク | 自己の治療費用 | 終身医療保険 定期医療保険 がん保険 生活習慣病保険 |
| ③働けないリスク | 家庭の収入を賄う | 就業不能保険 |
| ④介護のリスク | 自己の障害状態への備え | 介護保険 |
死亡のリスク
葬儀費用を保険でまかなう場合は通常、貯蓄型の生命保険である「終身保険」を活用します。終身保険であれば万が一のときに一定の金額を確保でき、かつ解約しても解約返戻金があるので掛け捨てにならないのがメリットです。
遺族の生活費は、国から遺族年金に加えて、「収入保障保険」で備えるのが有効です。収入保障保険は毎月10万円、15万円といったように年金月額(毎月の受取金額)を決めて加入します。そして、被保険者(保険の対象となる人)に万が一のことがあったときは保険期間が終わるまで毎月、加入時に指定した金額を受け取ることができます(一括で受け取ることも可能です)。
| 自営業 | 夫が会社員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均標準報酬月額 | ||||
| 25万円 | 35万円 | 45万円 | ||
| 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金∔遺族厚生年金 | |||
| 子供が3人 | 10.9万 | 14.3万 | 15.6万 | 17.0万 |
| 子供が2人 | 10.3万 | 13.7万 | 15.0万 | 16.4万 |
| 子供が1人 | 8.4万 | 11.8万 | 13.1万 | 14.5万 |
※金額はおおよそ
※給付は18歳到達年度の末日まで
教育資金については学資保険に加入すると、契約者である親に万が一のことがあった場合は以降の保険料を支払わなくても学資金を受け取れます。学資保険を利用しない場合は必要な金額を「定期保険」でカバーするという方法もあります。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
卒業までの総額
卒園・卒業までの総額
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 公立 | ¥649,088 | ¥1,926,809 | ¥1,462,113 | ¥1,372,072 |
| 私立 | ¥1,584,777 | ¥9,592,145 | ¥4,217,172 | ¥2,904,230 |
| 大学 | |
|---|---|
| 国公立 | ¥5,393,000 |
| 私立文系 | ¥7,308,000 |
| 私立理系 | ¥8,267,000 |
幼稚園~高校
出典:文部科学省「子どもの学習費調査」(平成30年度)大学
出典:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」(平成30年度)
病気やケガのリスク
病気やケガをして入院したときの医療費は医療保険でまかなうことができます。
医療保険は入院1日ごとに支払われる「入院給付金」がベースとなります。入院給付金は、会社員であれば1日当たり5,000円~1万円、自営業者であれば1万~1万5,000円程度が目安になります。高額療養費制度の利用による負担の減少や、傷病手当金として支払われるお金も考慮した上で金額を決めましょう。
また、がんの医療費に備えるため、がん保険に加入する方も多いです。医療保険は入院しないと基本的に給付金を受け取れませんが、がんは通院で治療することも最近は増えました。入院しなくてもお金を受け取れるがん保険が役立ちます。
さらに、がん以外の生活習慣病に備えるため、所定の条件に該当すると一時金がもらえるタイプの保険(3大疾病保険や特定疾病保険など)に加入するのもおすすめです。特に脳卒中はリハビリで長期間にわたって入院することもあるので、こうした事態を想定して備えることも大事です。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
働けないリスク
重い病気やケガが原因で働けなくなることに備える保険は「就業不能保険」や「所得補償保険」と呼ばれます。これらは被保険者が「就業不能」状態であると認定されたときに、あらかじめ決められた金額が毎月、支払われる保険です。
こどもが小さいうちに就業不能状態になると家計へのダメージが大きいので、保険金額は少し高めに設定しておくのが良いでしょう。収入保障保険とセットで検討してください。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
介護のリスク
先述の通り、若いうちに要介護状態になるリスクはそれほど高くありません。生命保険会社の介護保険への加入を考えるよりも、働けないリスクに備えて就業不能保険を優先するのがおすすめです。介護保険への加入は公的介護保険に加入する40歳を過ぎてからでも遅くはありません。
配偶者のリスク
配偶者のリスクも基本的には世帯主と同じですが、リスクの大きさに違いがあります。なお、ここで言う配偶者とは専業主婦(夫)やパートタイマーなど、世帯主と比べて収入が少ない人を想定しています。夫婦ともに家計を支えられるくらいの収入がある場合は世帯主の解説を参照してください。
死亡のリスク
教育資金や生活資金について世帯主の収入だけで確保できるのであれば、配偶者の死亡のリスクについては葬儀費用の準備があれば十分です。世帯主と同様に終身保険を検討してください。なお、配偶者がパートタイマーであっても、その収入がなくなると家計に影響がある場合は収入保障保険も検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
病気やケガのリスク
病気やケガのリスクについては基本的に世帯主と同じように考えてください。なお、医療保険の入院給付金の金額は、世帯主よりも少なめにしても良いかもしれません。
なお、妊娠しているときは加入できなかったり、特定の部位が保障されないという条件が付いたりすることが多いです。もし今後、妊娠の予定があるなら早めに検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
・女性疾病
働けないリスク
配偶者が働けなくなっても世帯主よりも家計に与える影響は小さいので、就業不能保険に加入する必要性はそれほど高くありません。どうしても必要と考えるのであれば検討してください。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
介護のリスク
介護のリスクについても世帯主と考え方は同様です。こどもが大きくなってから検討しても良いでしょう。
こどものリスク
こどもの備えについては、病気やケガのリスクを考えておけば十分です。
こどもの場合、健康保険を使える医療を受けたときの医療費のうち、自己負担分は自治体が負担してくれます。自治体によって対象となる年齢には違いがあり、中学校卒業までか高校卒業までのいずれかです。
ただし、入院したときに生じる食費や差額ベッド代は自己負担になりますし、付き添いにかかる費用を準備したいという方はこどもでも加入できる医療保険を検討してください。
また、こどもでも小児がんにかかる可能性はあります。こどものがんが心配なら、がん保険で一時金だけでも確保しておくのが良いでしょう。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
教育資金や住宅資金、老後資金を保険で備えるには?
先述した「将来に向けて準備した方が良いお金」については貯蓄だけでなく、保険を活用して備えることもできます。ここでは保険を活用して資金を準備する方法を紹介します。
(例)夫35歳 妻30歳の場合の年齢目安
| 子供 | 夫 | 妻 | |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 4歳 | 38歳 | 33歳 |
| 小学校 | 7歳 | 41歳 | 36歳 |
| 中学校 | 13歳 | 47歳 | 42歳 |
| 高校 | 16歳 | 50歳 | 45歳 |
| 大学 | 19歳 | 53歳 | 48歳 |
| 結婚 | 28歳 | 63歳 | 58歳 |
必要金額をおさらいする
幼稚園私立~小中高公立~大学私立文系の例
| 学校区分 | 必要額 | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 私立 | ¥1,584,777 |
| 小学校 | 公立 | ¥1,926,809 |
| 中学校 | 公立 | ¥1,462,113 |
| 高校 | 公立 | ¥1,372,072 |
| 大学 | 私立文系 | ¥7,308,000 |
| 結婚(※) | ー | ¥1,878,000 |
| 合計 | ¥15,531,771 |
※出典:「ゼクシィ結婚トレンド調査2019 親・親族からの援助総額の全国平均」
幼稚園私立~小中高公立~大学私立文系の例
教育資金
教育資金を貯めるために使える保険は主に以下の2つです。
学資保険
こどもの教育資金を準備する方法として、学資保険は定番です。学資保険は貯蓄型の保険であり、かつ契約者に万が一のことがあった場合は保険料の払い込みが免除され、学資金を受け取れる死亡保障の機能も付いています。
なお、学資保険は元本割れする商品があるので、貯蓄のつもりで加入するなら必ず元本割れしないものを選んでください。
終身保険
学資保険の代わりに終身保険を活用する方法もあります。終身保険を活用する場合は一定期間、解約返戻金の割合を通常の終身保険よりも抑えている「低解約返戻金型終身保険」に加入します。資金が必要となる時期に解約して解約返戻金を受け取り、教育資金に充てます。
なお、終身保険を利用する場合は早めに加入しないと、解約返戻金が払い込んだ保険料の総額よりも低くなります。終身保険を検討する場合は学資保険と比較して有利なほうを選んでください。
住宅資金
住宅資金を貯めるにあたり、教育資金と同様に終身保険を活用する方法もあります。
終身保険に加入しても、解約返戻金が払い込んだ保険料の総額を超えるまでには時間がかかるので、頭金を準備する方法としてはあまり向いていません。住宅資金の準備方法として終身保険を活用する場合は、将来の繰上返済の資金にする方が合っています。
また、積極的に資金を増やしたい場合は外貨建て保険や変額保険を活用することも検討してください。
外貨建て保険は一般的に、積立利率が円建ての保険よりも高く設定されています。また、為替相場の動向によっては大きく資金が増える可能性があります。ただし、日本円に換金するタイミングで円高になれば、払い込んだ保険料の総額よりも資金が少なくなるリスクがある点に注意が必要です。
変額保険とは、保険会社が預かった保険料の一部を通常の保険(定額保険)とは違う「特別勘定」で運用し、その結果によって保険金や解約返戻金が変動する保険のことです。運用がうまくいけば大きく資金が増える可能性があるものの、失敗すれば元本より少なくなるリスクがあります。
老後資金
老後資金を生命保険会社の商品で準備するなら、まずは個人年金保険を検討してください。
生命保険に加入して支払った保険料は「生命保険料控除」として節税効果がありますが、一定の要件を満たした個人年金保険は別枠の「個人年金保険料控除」になるのでさらに有利です。ただし、年金として受け取る金額が決まっているので、物価が上昇すると実質価値が目減りするデメリットもあるので注意が必要です。
貯蓄型保険を利用して老後資金を準備する場合は養老保険も活用できます。養老保険とは加入する期間が決められた貯蓄型の死亡保険で、満期を迎えても、保険期間中に死亡しても同額の保険金を受け取れるのが特徴です。養老保険に加入すれば、節税効果を得ながらお金を増やすことが可能です。
その他、住宅資金のところで解説した外貨建て保険や変額保険を活用することもできます。まずは個人年金保険があるので、いずれもリスクを許容できるのであれば利用を検討してください。
こどもが産まれたら備えはしっかりと
人生において最も保険のことをしっかり考えなければいけないのは、こどもが産まれたばかりのタイミングでしょう。
こどもが産まると、教育資金や遺族の生活費を確保する必要がありますし、自身の病気やケガの備え、働けなくなったときの備えなど考えなければならないことがたくさんあります。
一般の方が数多くの保険を検討するのは難しいので、プロに相談しながら自身に合った保険を見つけてください。