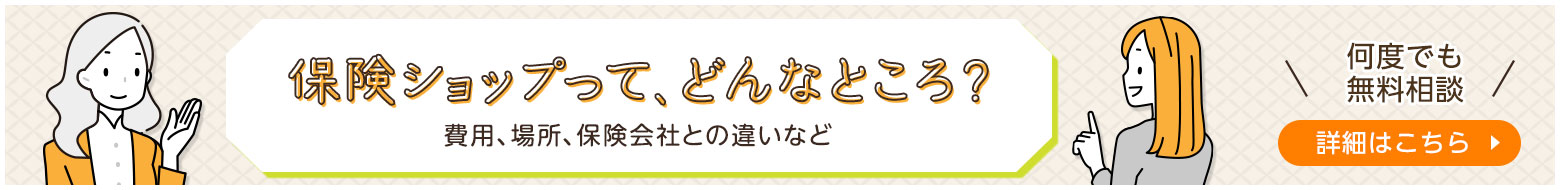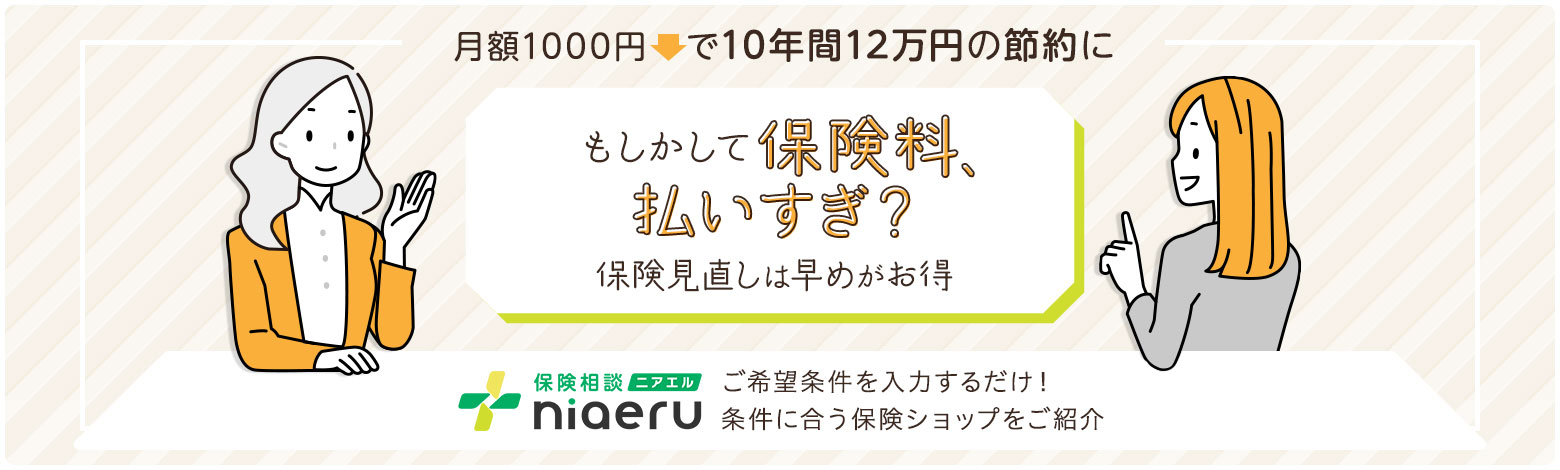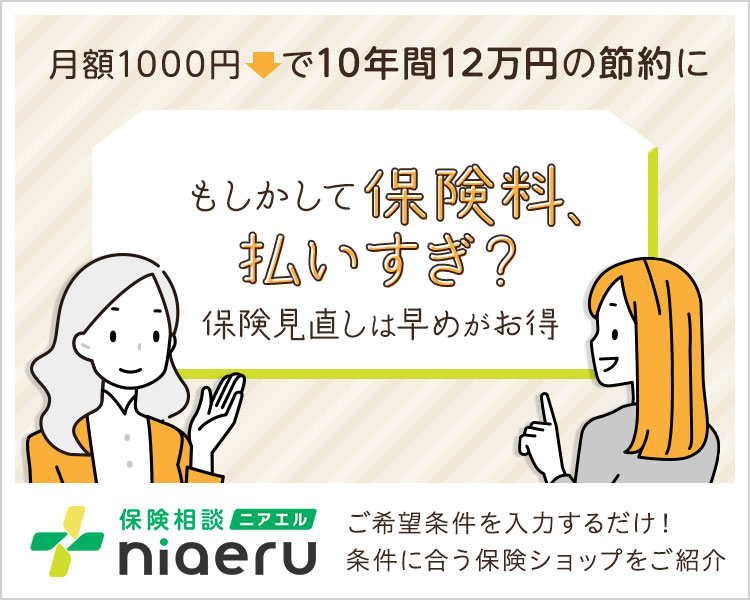こどもが生まれた場合、生活費だけでなく教育資金についても保険で備える必要があります。
こどもの教育資金のうち、大学への進学費用と初年度授業料は200万円から300万円ほど(※1)と高額です。
※1 参考:「 平成30年年度 日本政策金融公庫の教育費負担の実態調査結果 」入学費用と1年間の在学費用の合計
そのため、親に万一のことがあると、進学に必要な資金を準備できなくなり、こどもが希望の進路に進めない可能性があります。高額な教育資金に備えるには、ここでご紹介する2種類の保険が有効です。それぞれ特徴が異なるため、1つずつ確認していきましょう。
目次
学資保険
世帯主 役立ち度◎
学資保険は、こどもの教育資金を準備するための積立型の保険です。加入時に指定したタイミングで学資金を受け取ることができ、高額な進学資金に備えることが可能です。
学資保険に加入してから、契約者である親に万が一のことがあった場合は保険料が免除されます。保険金や学資金も予定通り受け取れます。保険料や保険金(額資金)受取りの条件は保険会社によって異なりますので、契約する前に確認しましょう。
学資保険に加入する方の多くは、大学進学時の資金を確保するために加入します。しかしプランによっては、学資金を受け取るタイミングが20歳や22歳と遅くなる場合もあります。資金を活用する時期と学資金を受け取るタイミングが合うよう計画を立てましょう。
さらに、契約者やこどもの年齢、払込期間によっては受け取れる学資金が払い込んだ保険料の総額を下回る保険会社もあります。特に2019年12月現在はマイナス金利の影響から、保険料の総額よりも受け取る学資金の合計が少なくなる元本割れを起こす保険会社も増えています。
そこで、学資保険に加入するときは、可能であれば保険料を年払い、もしくは前納するのも一つの方法です。支払い回数を少なくし、保険料を下げて積み立てるメリットを最大限に生かしましょう。
加えて学資保険の学資金を一時金で受け取った場合は、一時所得として扱われます。ただし、受け取った学資金から支払った保険料の総額を差し引いた額が50万円以下の場合、税金は課せられません。
学資保険に加入するときは、複数の保険商品の見積もりを比較し、支払保険料の総額、支払方法、返戻率、受け取り方法などを慎重に選ぶことで、効率的に教育資金が貯められるだけでなく、万が一の時も教育資金は確保できます。
終身保険(短期払)
世帯主 役立ち度◎
一生涯、死亡保障が続く終身保険の解約返戻金を、教育資金に充てる方法もあります。
特に、保険料を払い込む期間の解約返戻金が少ない低解約返戻金型は、通常の終身保険に比べて月々の保険料が安く、家計への負担も小さくなります。払込期間と受取時期を調整すれば、払った保険料の総額よりも解約返戻金が高くなる場合もあり、教育資金を確保する手段として利用できます。
ただし終身保険は、学資保険のように決まった年齢になると自動的に学資金が受け取れるわけではありません。また、保険会社や払込期間などによっては、解約返戻金が100%を割り込み元本割れすることもあるので慎重に検討しましょう。
終身保険は、もともと死亡保険ということもあり、万一の時は学資保険より多くのお金を残せる可能性があります。加えて終身保険は、学資保険のように学資金を受け取るタイミングを加入時に指定する必要はありません。「18歳で受け取る必要がなくなった」「結婚資金を援助するため受け取り時期を繰り下げたい」など、お金を受け取るタイミングを自由に設定できるのもメリットです。
終身保険で教育資金をまなかうのであれば、元本割れしないタイミングや、どの時点で解約返戻金の額がどれぐらいになるのかを見積もりながら検討しましょう。