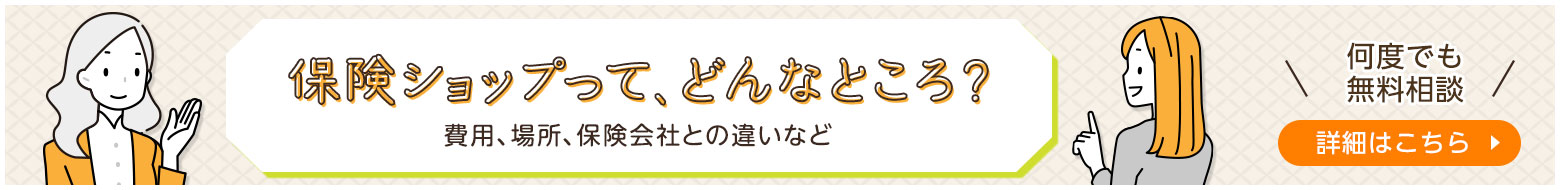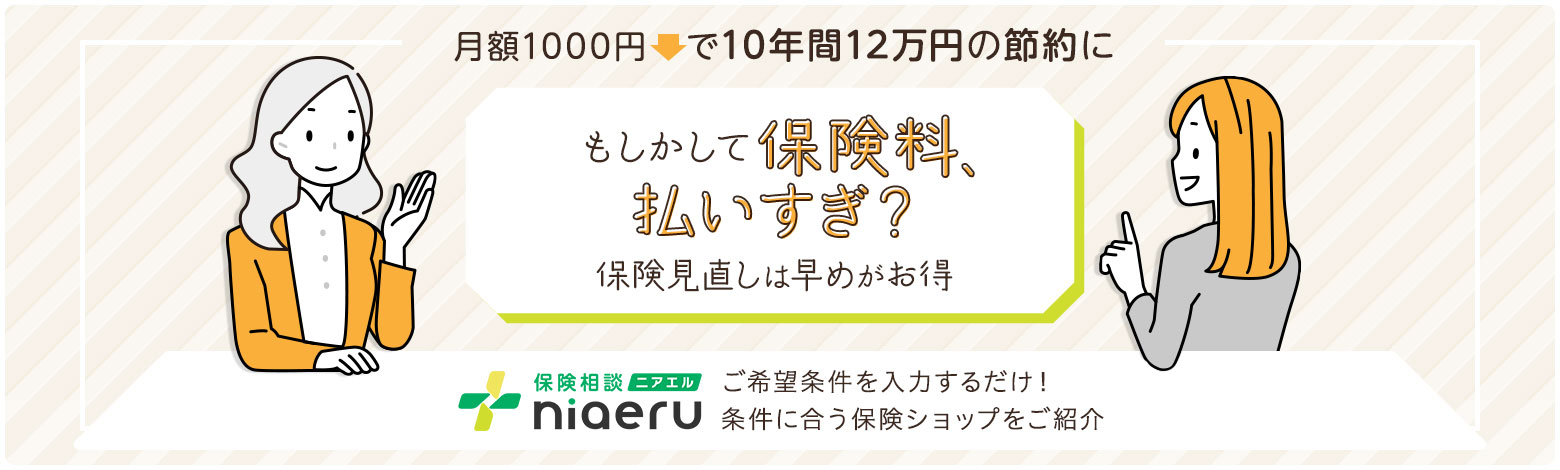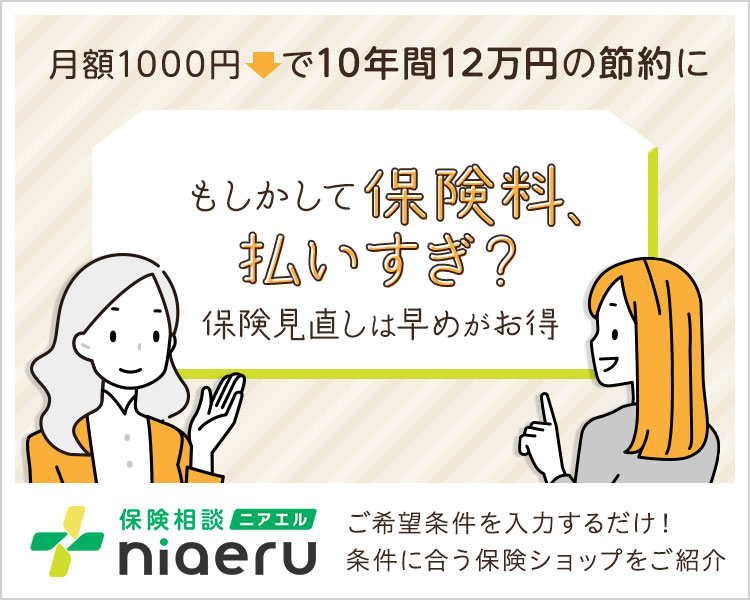人生にはさまざまなリスクがありますが、生命保険で備えられるリスクは主に以下の3つです。
・死亡時のリスク
・病気・ケガのリスク
・働けなくなった時のリスク
就職した時点で独身であれば、死亡時のリスクへ備えは葬儀費用の準備だけで十分です。
しかし、将来、結婚して家庭をもつようになると、遺族の生活費・教育資金を確保することも必要になります。一定の条件を満たしている場合、配偶者や子どもは国から遺族年金を受け取ることができますが、決して十分な金額とは言えないので、結婚した際は保険でしっかりとした保障を確保することが大切です。
独身でも大きな病気やケガで入院したときは医療費が必要になりますし、仕事を休んだことにより収入が減ることもあるかもしれません。こうした負担も保険でカバーすることが可能です。
また、病気やケガが原因で、健康な時と同じように働くことが難しくなることもありえます。障害年金や公的介護保険のような国の支援もありますが、それだけでは十分な生活費を確保できなくなる可能性があります。こうした事態についても民間の保険で備えることができます。
目次
将来に向けて準備した方がよい金額
リスクに対する備えのほか、住宅資金や老後資金など将来への備えについても準備を始めたほうがよいでしょう。これらはまとまった金額になるので、時間をかけて準備することをおすすめしています。
住宅資金については就職した時点で「いつまでにいくら貯めたい」と決めることは難しいかもしれません。しかし、例えば「30歳までに頭金を500万円くらい貯めておきたい」といったように目的を絞らず10年後、20年後にいくら貯めるということを漠然とでも考えておくと、計画的に貯蓄しているとマイホームが欲しくなったときに慌てることがありません。
また、老後資金については、かなり先の話なので、実感がわかないかもしれません。しかし、公的年金が十分にもらえないのではないか、という不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。
金融審議会の市場ワーキンググループが作成した報告書でも「夫65歳以上、妻60歳以上の無職世帯はおよそ2000万円の生活費が不足する」という指摘がなされました。何らかの形で備えが必要であることは間違いありません。
一度にまとまったお金を準備するのは大変ですが、就職したばかりであれば老後はかなり先の話なので時間を味方につけることができます。そのため、退職金の有無や目標から逆算して、毎月の積立額を考えてみるのがおすすめです。
| 住宅資金 | 就職時は「将来の住宅購入を目標にして積み立てを開始する」など目的を絞った貯蓄をするよりは、「10年後・20年後にいくら貯める」といった目標の立て方の方が現実的ではある。 | |
|---|---|---|
| 老後資金 | 退職金の有無によって毎月の積立額を計算するべき。老後資金に不足が無いよう、65歳で2,000万などの目標を立て、目標から逆算して定額の積立を開始した方が効率的に貯められる。 | |
想定されるリスクは時間の経過とともに変化する
人生において想定されるリスクの内容は時間の経過とともに変化します。例えば、独身である場合、家族のために用意する死亡保障はほぼ必要なく、葬祭費用の準備があれば十分といえるでしょう。そして、リスクに対して適切に備えるためにはそのリスクに合った保険を選ぶことが必要です。
世帯主として備えておくべきリスクと保険
ここでは、両親と同居している場合も便宜上、世帯主としています。
就職した時点で独身だとしても、結婚して家計を支える立場になれば、配偶者やこどものことを意識して保険を見直すことが必要になります。一度加入したらそのままにするのではなく、ライフイベントの変化や3~5年毎など定期的に保険を見直すことが大事です。
| リスク | 就職 | 保険の種類 |
|---|---|---|
| ①死亡のリスク | 自己の葬祭費用 | 定期保険 終身保険 収入保障保険 |
| ②病気・ケガのリスク | 自己の入院・治療費用 | 終身医療保険 定期医療保険 がん保険 生活習慣病保険 |
| ③働けないリスク | 自己の収入を賄う | 就業不能保険 |
| ④介護のリスク | 自己の障害状態への備え | 介護保険 |
死亡のリスク
独身であれば通常、養うべき家族がおらず、お墓の準備も不要であることが多いため、死亡時の備えとしては葬儀費用の準備があれば十分です。
この場合は貯蓄型の保険である「終身保険」を利用するのがおすすめです。
しかし、結婚してこどもが産まれたら、万が一のリスクは大きくなります。一定の要件を満たしている場合は国から遺族年金が支給されますが、決して十分な金額とは言えません。そのため、掛け捨て型の死亡保険である「定期保険」や「収入保障保険」を活用してしっかりと備えることが必要になります。
■リスクに備えるための保険
定期保険
終身保険
収入保障保険
病気・ケガのリスク
あまり想像できないかもしれませんが、誰しも病気やケガで入院するリスクはあります。そのため、入院費用として医療保険で備えておくことがよいでしょう。
医療保険に加入する場合は、入院1日あたりの給付金(入院給付金日額といいます)で備えることが必要です。具体的には、会社員や公務員なら5,000円~1万円、自営業者であれば1万~1万5,000円くらいは備えておくべきでしょう。
なお、健康保険には「高額療養費制度」という仕組みがあります。これは、医療費が高額になった場合でも、患者の自己負担額をおさえてくれるものです。入院費用についての備えを考えるときは、高額療養費制度についてしっかりと理解しましょう。
また、一生涯のうち日本人の2人に1人がかかると言われている「がん」についての備えも大切です。がんの治療は、入院よりも通院で行うことが増えています。それに加え、がんはいったん治っても再発する可能性が高いという特徴もあります。そのため、退院後の通院や働けなくなることなども考え、がんと診断確定された時点でまとまったお金(一時金)を受け取れるがん保険を検討するのがおすすめです。
以上のほか、心疾患や脳血管疾患などの生活習慣病についての備えも考えておいてください。重症の場合は、後遺症が残り、リハビリが必要になることがあります。
このような時は医療機関に対する支払いが増えるだけでなく、それまでと同じように働けなくなって収入が減ることが予想されます。こうしたリスクに備える場合は、生活習慣病を対象とした一時金型の保険を検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
終身医療保険
定期医療保険
がん保険
生活習慣病保険
働けなくなった時のリスク
大きな病気やケガが原因で身体の機能が低下し、それまでと同じように働けなくなるリスクもあります。このような事態になった場合、健康保険の傷病手当金や障害年金などの制度を利用することができますが、それだけでは生活費を十分にまかなうことは困難です。
こうしたリスクに備えるための保険として、就業不能と認定されたときに給付金を受け取れる「就業不能保険」があります。この保険は、病気やけがの後遺症で、働けなくなってしまった時に生活費を確保するうえで役立ちます。
■リスクに備えるための保険
就業不能保険
介護時のリスク
若いうちでも大きな病気やケガによって要介護状態になる可能性はゼロではありません。要介護状態になった時に利用できる制度としては公的介護保険がありますが、利用できるのは40歳以上であり、かつ65歳未満で適用されるケースはごく一部に限られています。
こうした事態に備えて民間の介護保険に加入しようと考える方もいるかもしれませんが、給付金の支給基準が公的介護保険に連動していることも多いので、備え方としてはあまりおすすめできません。それよりも、働けなくなった時のリスクに備えることを優先しましょう。
住宅資金を保険で準備するなら
住宅資金は貯蓄で準備しようと考える方が多いかもしれませんが、保険を利用して貯蓄をすることもできます。しかし、就職したばかりの方で、マイホームの計画を立てる方は少ないでしょう。ここでは、15年後、20年後、自由に使える資金を備えるために活用することができる保険について解説します。
-
住宅資金を貯めるのに役立つ保険
住宅資金を貯めるのに活用できるのが、貯蓄型の保険である終身保険です。終身保険を活用する場合は低解約返戻金タイプを選択し、できるだけ短期間で保険料の払込みを終え、お金が必要になったら解約して返戻金を受け取る形で利用するのがよいでしょう。
払い込んだ保険料より大きく増えることはありませんが、契約者死亡時には払い込んだ金額より多くの保険金が受け取れるといったメリットや、支払った保険料の全部または一部を「生命保険料控除」として扱うことができ、節税効果が期待できるなどのメリットがあります。
ただし、早期解約した場合には、解約返戻金がないか、あったとしてもごくわずかな金額になってしまう可能性があるので注意が必要です。
| 終身保険(短期払) | メリット | 契約者死亡時には払い込んだ金額より多くの保険金が受け取れる |
|---|---|---|
| デメリット | 早期解約した場合は契約返戻金がないか、あってもごくわずかな金額になる |
-
住宅資金を増やすのに役立つ保険
単にお金を貯めるだけでなく、増やしたい場合は外貨建て保険や変額保険という選択肢もあります。
外貨建て保険は、保険料を米ドル・豪ドルなどの外貨で運用する保険です。日本よりも市場金利が高いため、円建ての商品よりも高い積立利率が設定されており、為替の動向によって解約返戻金が増えることがあるのが魅力です。ただし為替相場は大きく変動することも多いので、円に換えて解約返戻金を受け取った時に元本割れするリスクもあります。
変額保険は、保険料を株式や債券で運用する保険です。運用が好調なら解約返戻金が増えるので資産運用の手段として利用できます。ただし、変額保険も外貨建て保険と同様に、運用状況によっては元本割れのリスクがあるので注意しましょう。
| 外貨建て保険 | メリット | 日本円建ての保険より解約返戻金が増えることがある |
|---|---|---|
| デメリット | 為替レートによっては円で解約返戻金を受け取った場合に減る可能性がある | |
| 変額保険 | メリット | 株式や債券で運用するため、定額保険に比べ解約返戻金が増える可能性がある |
| デメリット | 運用状況によっては定額保険より解約返戻金が減ることもある |
老後資金を保険で準備するなら
就職した時点で老後資金の心配をするのは気が早いと考える方もいるかもしれませんが、時間を味方につけることができるので、早めに備えることをおすすめします。無理のない金額でコツコツ続けることを検討してみてください。
老後資金を貯めるのに役立つ保険
老後資金を準備するために活用できる民間の保険の中で、代表的なのは個人年金保険です。個人年金保険は、一定の要件を満たすと「個人年金保険料控除」という形で所得控除を受けることができるので、節税効果が期待できます。
ただし、受け取る年金の金額が決まっているため、物価上昇に弱いという点には、注意してください。
また、一定期間(10年~30年程度)の死亡保障を得つつ、満期を迎えた時も同額の保険金を受け取ることができる「養老保険」も活用できます。養老保険には、死亡保険としても備えられ、満期時には死亡保障額と同額の満期金が受け取れるといったメリットがあります。その一方で、一般的には死亡保障機能がある分、個人年金保険に比べて利率は抑えられているといったデメリットもあるので、長い目で見るなら死亡保険と貯蓄性保険は別々に加入するのがおすすめです。
| 個人年金保険 | メリット | 個人年金保険控除により税メリットを受けられる |
|---|---|---|
| デメリット | 定額のため、年金額が物価上昇に見合わないことも | |
| 養老保険 | メリット | 死亡保険も備えられ、満期時には死亡保障額と同額の満期金が受け取れる |
| デメリット | 一般的には死亡保障機能がある分、個人年金保険に比べ利率は抑えられている |
老後資金を増やすのに役立つ保険
老後資金を増やすことに期待する場合、住宅資金を準備する手段と同様に外貨建て保険や変額保険を活用することができます。
老後資金の場合は住宅資金よりも運用する期間が長くなるのでより大きな効果が期待できますが、リスクも大きいことを理解しておく必要があります。特に為替相場の予想はプロでも難しいので、外貨建て保険を活用するときは十分に注意してください。
| 外貨建て保険 | メリット | 日本円建ての保険より解約返戻金が増えることがある |
|---|---|---|
| デメリット | 為替レートによっては円で解約返戻金を受け取った場合に減る可能性がある | |
| 変額保険 | メリット | 株式や債券で運用するため、定額保険に比べ解約返戻金が増える可能性がある |
| デメリット | 運用状況によっては定額保険より解約返戻金が減ることもある |
就職時に検討する保険についてのまとめ
社会人になり、毎月給与が入ってくると浪費をしてしまいがちです。また、生命保険の勧誘を受ける機会も増えるため、正しい知識がないと言われるがまま加入してしまい、ムダな保険料を払うことになりかねません。
そのため、保険について最低限の知識を身につけておき、必要な保険と、そうでない保険の判断をできるようにしましょう。
住宅資金や老後資金の準備については保険のほか、預貯金、確定拠出年金、持株会などさまざまな方法があるので、自身に合ったものを選ぶのがおすすめです。
就職した今のタイミングなら、時間を味方にできるのが何よりの強みです。おおまかでもいいので計画を立て、無理なくコツコツと資産形成を行いましょう。