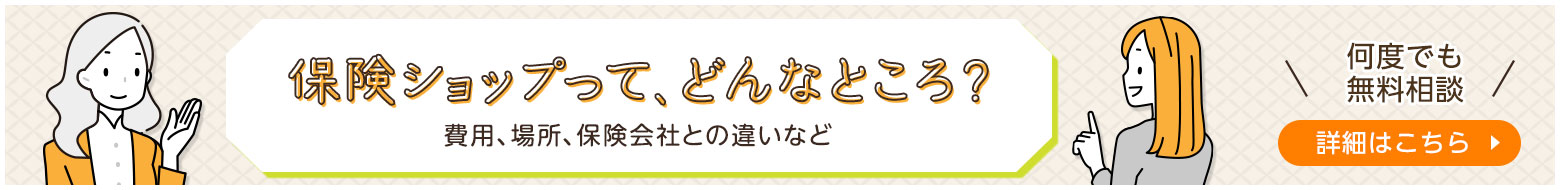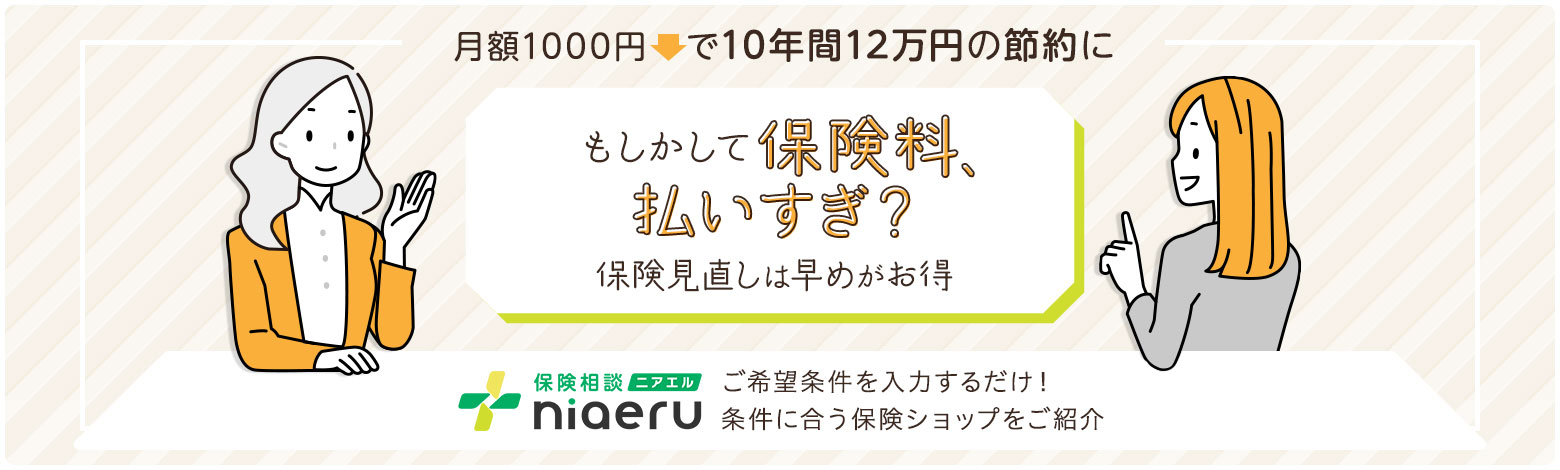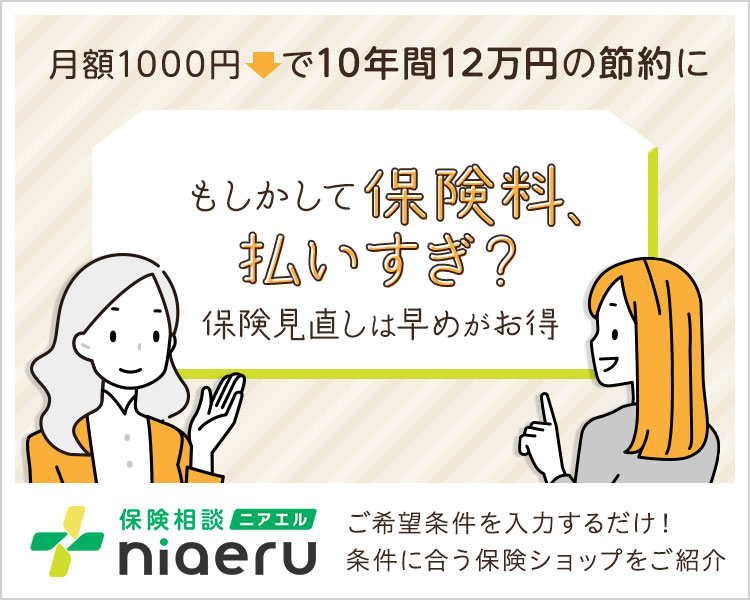結婚すると独身のときとは違い、配偶者に対する責任が生じます。将来、想定されるリスクにどう備えるか、きちんと考えることが大切です。
目次
結婚したときに想定されるリスクにはどんなものがある?
死亡のリスク
厚生労働省が発表した平成30年簡易生命表によると、男性の平均寿命は81.25年、女性の平均寿命は87.32年となっています。しかし、不幸にも若いうちに亡くなることもあります。
死亡した場合にすぐに必要となるお金は主に葬儀費用です。実家のお墓に入れない場合は墓石や永代供養などの費用も必要となります。また、共働きでない場合や配偶者に十分な収入がない場合は、遺族年金でまかなえない生活費を補填することも考えておく必要があります。
病気・ケガのリスク
若いうちはあまり大きな病気にかかるイメージが持てないかもしれませんが、大きな病気はある日突然かかるものです。がんと言えども決して例外ではありません。
万が一、大きな病気にかかれば治療のためにまとまったお金がかかるので、そのための備えをしておくことが必要です。
働けないリスク
重い病気や交通事故などが原因で後遺症が残り、健康なときと同じように働けなくなるリスクもあります。障害年金や障害者手帳も利用できますが、それでは十分な収入が得られないことが多いようです。
配偶者が専業主婦(夫)やパートタイマーであれば、そのリスクはより大きくなります。
介護のリスク
働けないリスクと同様に病気やケガが原因で、介護が必要になるリスクもあります。介護というと公的介護保険を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、公的介護保険に加入できるのは40歳以降であり、かつ65歳未満で利用できる人は限られています。
想定されるリスクにどう備える?
リスクに備える上で、保険はとても役立ちます。まずは、どんなリスクにどの保険が対応しているかを理解することが大切です。ここでは世帯主・配偶者に分けて、どんな保険を活用するのが良いか解説します。
なお、結婚したときは保険内容を変更する手続きが必要となります。なるべく早めに保険会社へ連絡して以下の項目を変更しましょう。
・保険契約者名・・・改姓した方は手続きが必要です。また、必要であれば契約者を世帯主に変更することもできます。
・住所、電話番号
・口座名義人・・・改姓した場合は手続きが必要です。世帯主の口座から保険料を引き落とすこともできます。
・保険金や給付金の受取人・・・保険金や給付金の受取人を世帯主や配偶者に変更する場合は手続きが必要です。
世帯主のリスクに対する備え方
世帯主でも配偶者でも想定されるリスクは同じですが、その大きさや備え方には違いがあります。そこで、まずは世帯主の備え方について解説します。
| リスク | 結婚 | 備える保険の種類 |
|---|---|---|
| ①死亡のリスク | 自己の葬祭費用 | 定期保険 終身保険 収入保障保険 |
| ②病気・ケガのリスク | 自己の入院・治療費用 | 終身医療保険 定期医療保険 がん保険 生活習慣病保険 |
| ③働けないリスク | 自己の収入を賄う | 就業不能保険 |
| ④介護のリスク | 自己の障害状態への備え | 介護保険 |
死亡のリスク
先述の通り、人が亡くなると葬儀費用やお墓代などが必要になりますが、こうしたリスクに保険で備える場合は通常、貯蓄型の死亡保険である「終身保険」が利用されます。
終身保険であれば、被保険者(保険の対象となる人)が死亡または高度障害状態になったときは保険金が受け取れますし、または、解約した場合は解約返戻金を受け取れるので保険料が掛け捨てになりません。ただし、契約してから短期間で解約すると、払い込んだ保険料の総額と比べて戻るお金が少なくなる点に注意が必要です。また、掛け捨ての「定期保険」よりも保険料が高くなることも注意が必要です。
世帯主が死亡すると配偶者の生活費が不足するリスクもありますが、配偶者が正社員として仕事に復帰し、十分な生活費を稼ぐ力があればそれほどリスクは高くありません。ただ、心配であれば毎月の収入を補う「収入保障保険」に加入して備えるのも有効です。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
病気・ケガのリスク
入院したときの医療費や、入院で減少が見込まれる収入を補うためには、入院日数に応じて給付金を受け取れる医療保険が役立ちます。医療保険の主な保障である入院給付金は、会社員であれば1日5,000円~1万円、自営業者であれば1万~1万5,000円程度で加入するのが目安です。
医療保険には一生涯の保障が得られる「終身医療保険」と、一定期間の保障が得られる「定期医療保険」の2種類があります。更新がなく、保険料が生涯変わらない(上がらない)保険で備えたいなら終身医療保険、5年・10年などの更新時に保険料は上がりますが若い時期は保険料を安く抑えられる保険で備えたいなら定期医療保険を選ぶのがおすすめです。
医療費に備える保険の中には、がんに特化した「がん保険」もあります。がん保険の特徴は、がんと診断されると50万~200万円程度のまとまったお金を受け取れる「診断給付金(診断一時金)」を受け取れる点です。
また、がん以外の生活習慣病に備えたい場合は「三大疾病保険(特定疾病保険)」があります。三大疾病とはがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞(急性心筋梗塞)、脳卒中のことですが、これらに加えて高血圧性疾患や糖尿病、慢性腎不全なども幅広く対象にしている保険商品もあります。三大疾病保険は所定の状態と認定されると一時金が受け取れる商品が多いです。ここでいう所定の状態とは、60日以上、労働の制限を必要とする状態が続いたり、言語障害などの後遺症が続くことなどが挙げられます。
なお、これらの保険を検討する際には、健康保険の「高額療養費制度」や「傷病手当金」の制度について知っておくことが大切です。
高額療養費制度を活用すれば、医療費が高額になっても自己負担は一定の水準に抑えられますし、会社員や公務員であれば傷病手当金を受け取れるので、仕事を休むことによる収入の減少を抑えることが可能です。保険はその上で見込まれる不足分を補うものと捉えてください。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
働けないリスク
重い病気やケガが原因で就業不能状態になると、収入が大きく減少するリスクがあります。一定の要件を満たしていれば障害年金が受け取れますが、2019年12月現在、障害等級1級で年額97万4125円、2級で77万9300円なので、決して十分な金額とは言えません。
このようなリスクに備えるためには「就業不能保険」または「所得補償保険」に加入するのが有効です。これらは被保険者が就業不能状態と認定されると、契約時に決めた給付金を月ごとに受け取り、生活費の不足を補える保険です。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
介護のリスク
要介護状態に備えて生命保険会社の介護保険に加入する方法もあります。ただ、生命保険会社の介護保険は公的介護保険の要介護度に連動して給付金の支払いを決める商品が多いです。公的介護保険は40歳以降でないと加入できないため、生命保険会社の介護保険に加入するよりも、働けないリスクに備えた方が良いでしょう。
配偶者のリスクに対する備え方
ここでは配偶者と世帯主との違いを明らかにしながら、配偶者が保険でリスクに備えるための考え方を解説します。
なお、ここで言う「配偶者」とは、専業主婦(夫)やパートタイマーなど、世帯主よりも収入が少ないケースを想定しています。配偶者の収入が世帯主と同程度の場合は世帯主の解説を参照してください。
死亡のリスク
死亡したときに葬儀費用やお墓代などがかかる点では世帯主と変わりありません。ただし配偶者が死亡しても、家計を支える収入を得ているのはもともと世帯主です。生活費も1人分減ることを考えれば、収入保障保険に加入して生活費の不足を補う必要はないでしょう。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
病気・ケガのリスク
病気やケガの備え方については世帯主と同じです。ただし、収入の減少を補う必要がないのであれば、世帯主の目安よりも入院給付金の額は低く設定しても良いでしょう。
がんやその他の生活習慣病についても同様で、収入が全くないか、世帯主より少ない場合は保険金額をやや少なめにするのも一つの考え方と言えます。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
・女性疾病
働けないリスク
収入が全くない専業主婦(夫)の場合は就業不能保険に加入して備える必要はありません。ただし、パートタイマーとして月数万円程度を稼ぐ配偶者でも、仮にその収入がなくなると困ると考えているのであれば加入を検討してください。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
・終身保険
・収入保障保険
介護のリスク
介護のリスクについての備え方は世帯主の場合と同じです。40歳を超えるまでは、働けないリスクを優先しましょう。
住宅資金や老後資金の準備で保険を活用するには?
住宅資金や老後資金も保険で準備する方法があります。ここでは保険を活用してこれらの資金をどう準備すれば良いか解説します。
住宅資金の保険による備え方
貯蓄型の生命保険である終身保険は、住宅資金の準備にも活用できます。
終身保険は加入してから一定の期間が経過すると、払い込んだ保険料の総額よりも解約返戻金の額が大きくなるタイミングが訪れます。保険料は生命保険料控除として扱えるので節税効果があり、両方の効果を得られれば利回りは銀行預金よりも高くなることが期待できます。
ただし、払い込んだ保険料の総額を上回るためには最低でも15年くらいの期間が必要なので、短期間で頭金を準備するのには向いていません。そのため、終身保険を利用して貯めたお金は住宅ローンを繰上返済するための資金として活用する方が向いています。
| 終身保険(短期払) | メリット | 契約者死亡時には払い込んだ金額より多くの保険金が受け取れる |
|---|---|---|
| デメリット | 解約までに期間によって、解約返戻金が払い込んだ金額よりも少なくなる場合がある |
また、資金が減るリスクを許容できるのなら、外貨建て保険や変額保険を活用することもできます。
外貨建て保険は積立利率が円建て保険よりも高く、タイミングが良ければ為替差益も得ることができて一石二鳥の効果があります。ただし、為替相場の動向によっては受取金を円に交換した後、元本割れするリスクがあるので注意してください。
変額保険とは定額保険と別勘定で運用する保険で、運用成績が良ければ保険金や解約返戻金が増えます。しかし、運用に失敗すれば逆に減ってしまうので、外貨建て保険と同様にリスクがあることに注意が必要です。
| 外貨建て保険 | メリット | 日本円建ての保険より解約返戻金が増えることがある |
|---|---|---|
| デメリット | 為替レートによっては円で解約返戻金を受け取った場合に減る可能性がある | |
| 変額保険 | メリット | 株式や債券で運用するため、定額保険に比べ解約返戻金が増える可能性がある |
| デメリット | 運用状況によっては定額保険より解約返戻金が減ることもある |
老後資金の保険による備え方
民間の生命保険会社の商品で老後資金に備えるなら、まず検討するのは個人年金保険です。
個人年金保険に加入して支払った保険料は「個人年金保険料控除」として扱われ、他の生命保険料控除とは別枠なので、その効果は大きいです。ただし、個人年金保険は契約期間が長くなるので、その間に物価が上昇すると実質の価値が目減りする点に注意が必要です。
また、貯蓄型の生命保険として「養老保険」という商品もあります。養老保険は満期を迎えても、保険期間中に被保険者が死亡しても同額の保険金を受け取ることができるのが特徴です。終身保険と同様に支払った保険料は生命保険料控除されますし、無事に満期を迎えれば払い込んだ保険料よりも多くのお金を受け取れるので、老後資金の準備に活用できます。
| 個人年金保険 | メリット | 個人年金保険控除により税メリットを受けられる |
|---|---|---|
| デメリット | 定額のため、年金額が物価上昇に見合わないことも | |
| 養老保険 | メリット | 死亡保険も備えられ、満期時には死亡保障額と同額の満期金が受け取れる |
| デメリット | 一般的には死亡保障機能がある分、個人年金保険に比べ利率は抑えられている |
その他、住宅資金のところで解説した外貨建て保険や変額保険も老後資金の準備に役立てられます。メリットやデメリットは住宅資金を準備する場合と同様なので、よく理解した上で活用してください。
| 外貨建て保険 | メリット | 日本円建ての保険より解約返戻金が増えることがある |
|---|---|---|
| デメリット | 為替レートによっては円で解約返戻金を受け取った場合に減る可能性がある | |
| 変額保険 | メリット | 株式や債券で運用するため、定額保険に比べ解約返戻金が増える可能性がある |
| デメリット | 運用状況によっては定額保険より解約返戻金が減ることもある |
結婚したばかりなら死亡保障以外に重点を置くべき
子どもがいない家庭の場合、死亡保障は葬儀費用程度の準備があれば十分で、高額の保障は必要ありません。死亡保障より病気やケガの保障、働けないときのための保障に重点を置いたほうが良いでしょう。
なお、女性が医療保険に加入する場合、妊娠してからだと加入できなかったり、加入しても特定部位の病気は保障されない場合もあります。妊娠・出産を計画している場合は早めに検討することが大切です。
女性が医療保険に加入する場合は「女性疾病特約」を付加することで、女性特有の病気にかかった際に給付金を上乗せされます。単に医療費に備えるだけでなく、諸雑費の支出にも備えたいのであれば、女性疾病特約を付加することも検討してください。