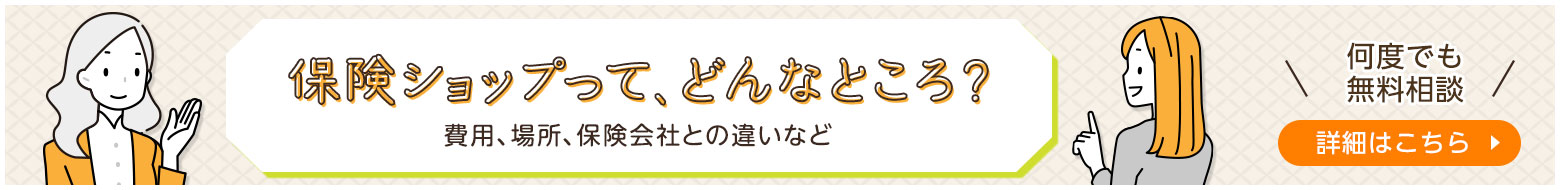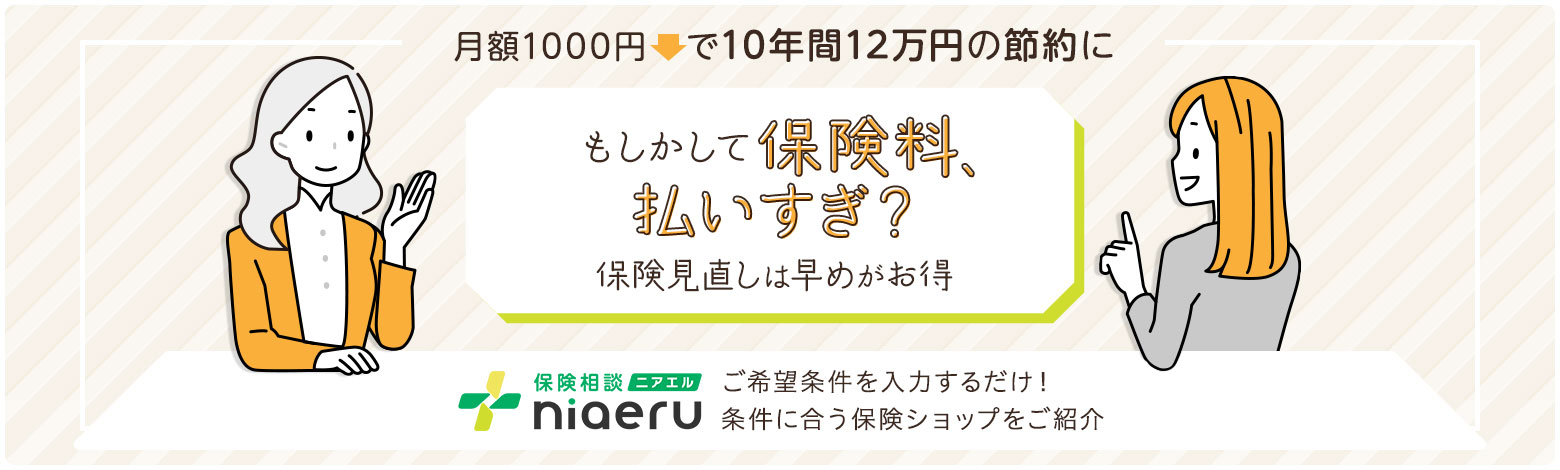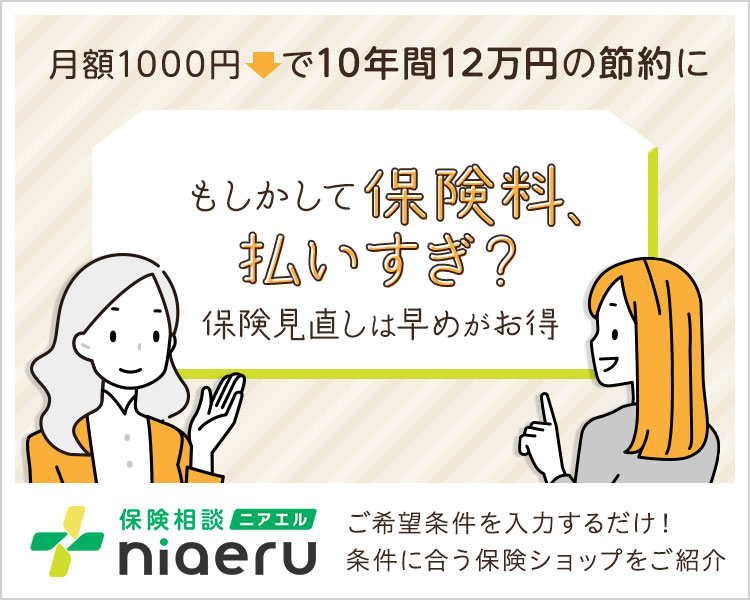目次
定年退職時に想定されるリスクとは?
定年退職を迎えると、主な収入源が勤労収入から年金に変わる人が多くなります。
しかし、引退したからといって、決して生きていく上でのリスクがなくなるわけではありません。現役の時と比べてその内容も変化しますので、それぞれのリスクについて適切に対処することは引き続き必要です。
定年退職時において想定されるリスクには、以下のようなものがあります。
・死亡のリスク(葬祭費用や相続費用のリスクなど)
・病気・ケガのリスク(入院・通院により生じる医療費のリスク)
・働けなくなった時のリスク(生活費が不足するリスクやリハビリ費用のリスク)
・介護時のリスク(介護施設の費用や在宅サービスを利用する時の費用のリスク)
これらのリスクについては保険を活用することで備えることができます。ただし、世帯主と配偶者ではリスクの大きさやその内容に違いがあります。
そこで、以下では世帯主と配偶者に分け、それぞれのリスクの内容と保険での備え方についてみていきましょう。
想定されるリスクに対する保険での備え方
定年退職後は年金を受給できるため、世帯主に万が一のことがあっても若い世代と比べて生活費用が不足するリスクが小さくなります。その代わり、病気やケガで入院・通院するリスクが高くなるので、医療費の備えをしっかりしておくことが大事です。また、保険を相続用に活用することも有効です。
世帯主
定年退職後であっても、世帯主のリスクに対する備えは大事です。相続の準備・対策を検討することが必要になる方もいるので、この機会に時間をとってしっかり見直しましょう。
死亡のリスク
世帯主が死亡のリスクに備える場合は以下の3点について検討しましょう。特に、生活費用については年金が関連するので正しく理解することが大事です。
・葬祭費用
一般財団法人日本消費者協会の「第11回 葬儀についてのアンケート調査報告書」(2017年1月)によると、葬祭費用の全国平均は約195万円です。この資金を保険で準備する場合は貯蓄型の保険である「終身保険」を活用するのが一般的です。
60歳を超えていても健康状態に問題がなければ加入できますが、保険料は若い世代よりも高くなるので注意してください。また、お墓の準備ができていない場合はお墓代も葬祭費用に上乗せすることが必要です。
・生活費用
配偶者が自身の老齢年金やそれまでの貯蓄で生活できれば備えは必要ありませんが、世帯主が死亡しても遺族基礎年金は、生計を維持している「子」(18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)がいないと受け取れないため、注意が必要です。
また、遺族厚生年金は世帯主の老齢厚生年金額(報酬比例部分)の4分の3に相当する金額が、自身の老齢厚生年金を上回る場合に受け取ることができます(自身の老齢厚生年金と併せてなので、いずれか多い金額)。
配偶者が自身の老齢年金を受給していないうちに世帯主が死亡すると、受給できるのは遺族厚生年金のみとなります。この場合は生活費が不足するリスクがあるので、定期保険に加入して不足を補うことを検討してもいいでしょう。ただし終身保険と同様、若い世代と比べて保険料は高くなります。
・相続費用
資産があり相続税の納税が見込まれるときは、生命保険を活用することで節税することができます。
保険金の受取人を法定相続人として生命保険に加入する場合、世帯主の死亡によって法定相続人が受け取る保険金はみなし相続財産として課税の対象となりますが、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるからです。この場合は一時払いの終身保険の活用を検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
病気・ケガのリスク
・入院時
厚生労働省が公表している「平成29年(2017)患者調査の概況」によると、50歳代の入院患者数が10万2,500人であるのに対し、60歳代の入院患者数は20万7,300人と2倍以上になっています。
高齢になるとこのように入院する確率が上がるだけでなく、入院期間も長くなる傾向があるので、医療保険に加入していないのであれば加入を検討しましょう。なお、一生涯の保障が得られる終身医療保険がおすすめです。
・がん
厚生労働省が2017年に公表した「人口動態統計月報年計」によると、日本人の死因の第1位はがん(悪性新生物)となっています。また、およそ2人に1人(男性62%、女性47%)が生涯でがんにかかるとのデータもあります。いつ罹患しても満足な治療を受けられるように備えるのであれば、がん保険への加入も検討してください。
・生活習慣病
厚生労働省が公表している「人口動態統計月報年計」(2018年)によると、死亡数はがん、心疾患、老衰、脳血管疾患の順に多くなっています。
がん・心疾患(急性心筋梗塞)・脳血管疾患(脳卒中)は「3大疾病」と呼ばれており、3大疾病保険に加入していると、これらの病気にかかって所定の状態になった時に保険金が支払われます。また、糖尿病や高血圧性疾患など他の生活習慣病も含めて保障する「特定疾病保障保険」という商品もあります。
これらは医療保険と違ってまとまった一時金を受け取れるのが特徴なので、生活習慣病に備える場合は加入を検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
働けなくなった時のリスク
重い病気や交通事故などが原因で働くことができない状態(就業不能状態と言います)になった時は、収入が減少して生活費が不足するリスクがあります。ただし、老齢年金を受給しながら働いているのであれば収入が途絶えるわけではないので、働けなくなった時のリスクに備える必要はありません。
また、老齢年金の受給開始前なら年金の繰上げ受給も利用できます。受給を1ヵ月繰り上げると0.5%減額されるので、例えば1年早く受給を開始すると0.5×12ヵ月=6%、1年6ヵ月早く受給を開始すると0.5×18ヵ月=9%が減額されます。なお、いったん受給を開始すると生涯、その減額された年金額のままになる点に注意が必要です。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
介護時のリスク
65歳以上であれば、要支援または要介護認定を受けると公的介護保険を利用することができます。利用限度額は要介護1なら16万5,800円、要介護5なら35万8,300円(いずれも月間)で、介護サービスを利用した場合は費用のうち1割を負担することになります。
要介護度が上がると、たとえ1割の負担であっても総額では大きな負担になります。また、限度額を超える住宅の改修(手すりの設置など)や福祉用具の購入、高額な入居金のかかる施設の利用を想定して備えをしたい場合は生命保険会社の介護保険の利用も検討してください。なお、1ヵ月に支払った介護サービスの自己負担が所定の上限を超えた時は、超えた分の払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」についても理解しておきましょう。
配偶者
配偶者のリスクについても、医療費の備えを充実させるべき点は世帯主と変わりません。他のリスクよりも優先させましょう。
死亡のリスク
死亡時の葬祭費用に対する備え方は世帯主と同様なので、保険で備える場合は終身保険を活用してください。お墓代が必要なら上乗せする点も同じです。相続費用も配偶者自身に資産がある場合は一時払いの終身保険で非課税枠を活用しましょう。生活費用については世帯主自身に老齢年金があるので、配偶者の死亡を想定して保険に加入する必要はありません。
■リスクに備えるための保険
・定期保険
・終身保険
・収入保障保険
病気・ケガのリスク
・入院時
高齢になると入院する確率が上がる点や、入院期間が長くなる傾向にある点は世帯主と同じです。そのため、健康状態に問題がなく医療保険に未加入であれば、今からでも加入を検討してください。一生涯の医療保障を確保できる終身医療保険がおすすめです。
・がん
がんの備えについては入院日数が短期化しているものの、高齢になるほど長くなる傾向にあります。また、通院のみでの治療も増えているため、入院しなくても給付金の支払いを受けられるがん保険に加入していると安心です。
なお、高齢になると乳がん・子宮がん・卵巣がんといった婦人科系のがんにかかる人の割合は減っていく傾向にありますが、70歳代後半までは乳がんにかかる割合は高いです。そのため、医療保険に女性疾病特約を付加して備えることも検討してください。
生活習慣病の備えも世帯主と基本的に同じです。3大疾病保険や特定疾病保障保険などの一時金型の保険による備えを検討しましょう。
■リスクに備えるための保険
・終身医療保険
・定期医療保険
・がん保険
・生活習慣病保険
・女性疾病
働けなくなった時のリスク
世帯主の定年退職後に配偶者が働いていて収入があったとしても、老齢年金の受給が開始されていれば、配偶者の収入がなくなったとしても問題になることは少ないでしょう。そのため、就業不能保険に加入して備える必要性はありません。
■リスクに備えるための保険
・就業不能保険
・終身保険
・収入保障保険
介護時のリスク
介護のリスクに対する備え方も基本的に世帯主と同じです。女性は平均余命が男性よりも長く、介護保険サービスを利用する割合も男性より高いというデータがあるので、よりしっかりした備えが必要です。
なお、女性の場合は骨粗鬆症や関節リウマチの罹患率が男性よりも高いです。こうした疾患をきっかけとして要介護状態になる可能性もあることを知っておいてください。
火災保険は保険期間や保険金額を確認しましょう
過失で自らの家が失火した時だけでなく、近所からの類焼であったとしても、住宅や家財に対して生じた被害は自らの火災保険でまかなうことが必要です。なぜなら、日本には「失火責任法」という法律があり、火元に故意または重過失がない限り損害賠償を請求することができないからです。
なお、火災保険の更新を忘れていると補償されませんので、保険が有効であるかどうかを確認してください。
また、保険金額が時価になっていると、住宅が全焼した場合は建て直す(買い直す)だけの保険金が受け取れません。近年は、新しく建て直すことができるだけの保険金を受け取れる「新価(再調達価額)」での契約が主流なので、もし時価になっているのなら契約内容を変更することをおすすめします。
火災保険は火災の被害だけでなく、台風や雪災、盗難による被害など、幅広く日常生活のトラブルを補償してくれる優れた商品です。どんな時に保険金を受け取ることができるのか、この機会に確認しておいてください。
■モノへの備えの保険
・火災保険
結論:医療費や介護費用の備えをしっかりと
老齢年金を受給する年齢になると生活費が不足するリスクが大きく減り、代わりに医療費や介護費用が生じるリスクが高くなります。
なお、生命保険文化センターの「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護期間が10年以上に及んだ方の割合は14.5%となっています。
介護期間がこれだけ長くなると費用の負担はかなり大きくなります。こうした事態も想定し、しっかり備えをしておきましょう。