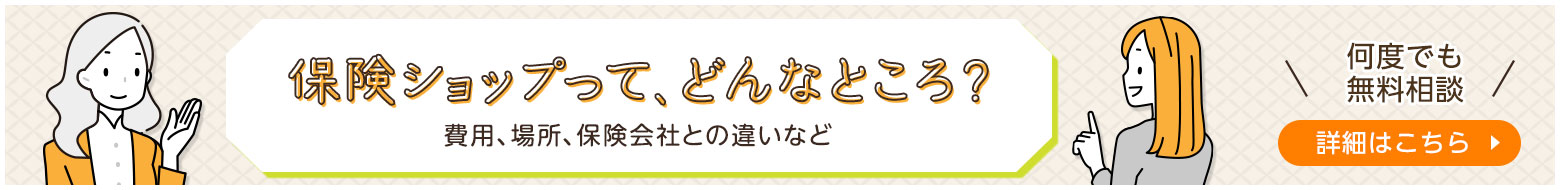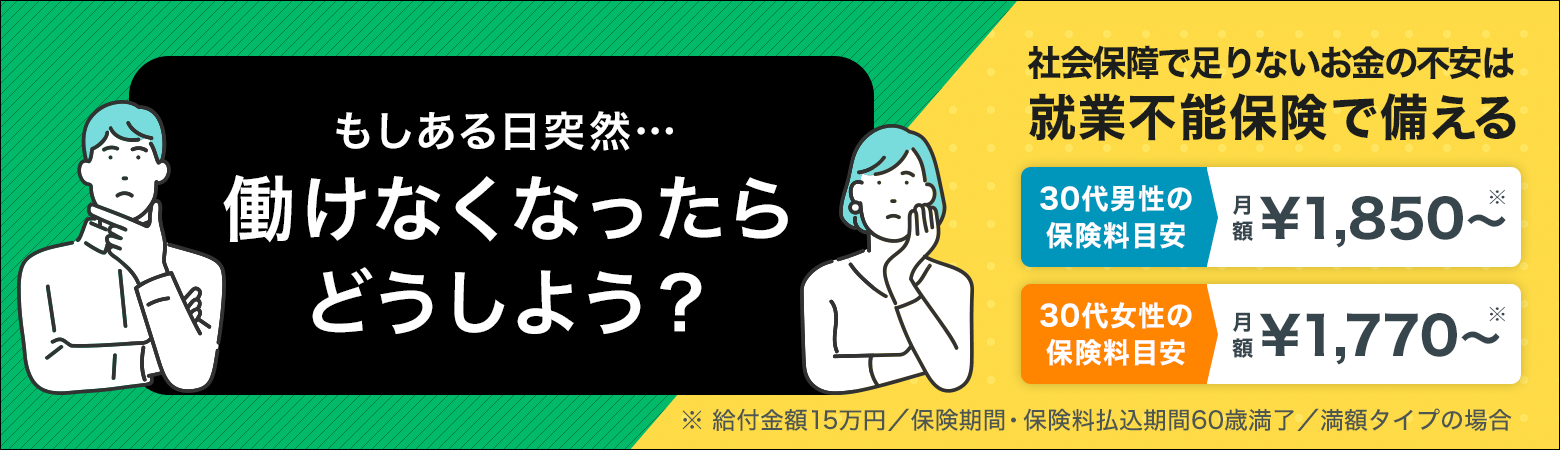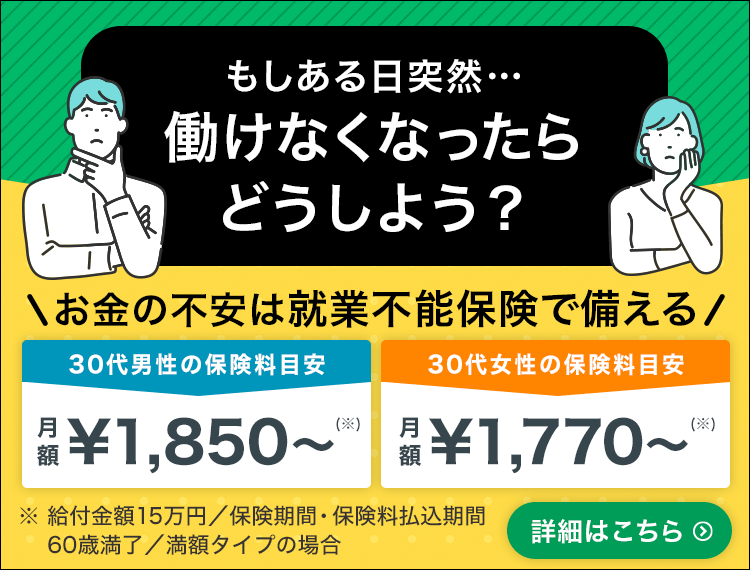プロの保険相談なら、取扱保険会社数の多い保険ショップがおすすめです。
目次
糖尿病の治療方法
一般的に「病気の治療」といえば、薬物療法や外科治療が思い浮かびます。
しかし日本人に多い糖尿病(2型)の治療は、まず食事療法や運動療法といった生活習慣の改善から始めるケースがほとんど。自己管理によって、ある程度病気の進行をコントロールできるのが糖尿病治療の特徴です。
<糖尿病の治療方法>
- ・食事療法:血糖値の急上昇に気をつけながら、バランスの良い食事を適切な量・タイミングでとる
- ・運動療法:血糖値を下げる有酸素運動や筋トレを日常的に行う
- ・薬物療法:糖尿病によって働きが低下してしまったインスリンというホルモンの働きを活発にするための飲み薬や血糖値を下げるためのインスリン注射を行う
特に食事は糖尿病治療の第一歩として非常に重要で、糖尿病の改善だけではなく予防にも効果があります。「糖尿病ではないけれど不安がある」人も、以下のポイントを見て日々の食事を見直してみましょう。
<糖尿病の食事療法のポイント>
- ・自分の体に適したエネルギー量(カロリー)の食事をとる
- ・朝食抜きやまとめ食いは避け、朝・昼・夕食と規則正しく食べる
- ・血糖値が上がりにくい食べ方を心がける:食物繊維が豊富な野菜→肉や魚、卵といったタンパク質→血糖値が上がりやすいご飯やパンなどの炭水化物は最後に食べる
糖尿病の治療費用
糖尿病の平均的な医療費は月額約6,000円(公的医療保険の3割負担分)とも言われています。ただ、実際の治療費は病気の進行状況と治療の内容によって大きく変わるので留意が必要です。
※出典:医療経済研究機構「政府管掌健康保険における医療費等に関する調査研究報告書」(平成15年度データ)
「糖尿病予備軍」の段階で食事療法だけであれば、比較的治療費も抑えやすいでしょう。しかし飲み薬やインスリン注射といった薬物療法を継続して受ける場合は、治療費の負担も増えてきます。
一度薬を飲み始めると一生飲むことになるケースもあり、病気が重症化すれば人工透析が必要になってしまう可能性も。自己管理の徹底と、万が一に備えた治療費の準備が必要です。
ここでは、糖尿病情報センターの情報を元に、投薬なしのケースとありのケースにわけて、治療費の目安をご紹介します。
ケース1 投薬なし、食事・運動療法のみの治療費
投薬(薬物療法)は一切なく、食事と運動療法のみの方が受診(検査と診察)した際にかかる治療費の目安は以下のとおりです。
・月額の治療費(医療費):公的医療保険の3割負担分で1,980円
※通院は月に1回とし算出
※保険点数は2020年4月診療報酬改定後の値で算定
出典:国立研究開発法人 国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病とお金のはなし」の「投薬がない方、もしくは飲み薬だけの方の場合(例)」の例1)より
この場合、特別な食事メニューや運動用品の購入は必要なく、日々の食事の仕方や運動を習慣付けることで治療できます。そのため大きな治療費になることはなく、検査料や診察料など病院にかかるための受診費用のみ必要です。
ケース2 投薬あり、経口薬療法の場合
経口薬療法で治療する場合、治療費の目安は以下のとおりです。
・月額の治療費(医療費):
受診と経口薬1種類を処方されている場合:公的医療保険の3割負担分で3,880円
受診と経口薬3種類を処方されている場合:公的医療保険の3割負担分で4,780円
※通院は月に1回とし、処方は30日分で算出
※保険点数・薬価は2020年4月薬価・診療報酬改定後の値で算定
出典:国立研究開発法人 国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病とお金のはなし」の「投薬がない方、もしくは飲み薬だけの方の場合(例)」の例2)・例4)より
上記は1種類または3種類の飲み薬を院外処方された場合の目安で、外来診察料、処方せん料、調剤料、薬剤料などを含めた費用となります。経口薬3種類の場合は毎月5,000円近く、と年間で6万円もの負担になるため、この先も薬を飲み続けることになれば生涯を通じて結構な負担になるのではないでしょうか。
糖尿病の治療に備えられる保険の種類
糖尿病の治療が始まり毎月通院・投薬治療をすることになれば、年間数万円もの費用負担が発生する可能性もあります。
そうした不安に備えられるのが、民間の保険商品です。
ここでは、糖尿病に備えられる保険商品の種類を紹介します。
①一般的な医療保険:一般的な病気・ケガを保障する保険。糖尿病も保障の対象になるため、糖尿病で所定の「通院」「入院」「手術」をしたときに一定の給付金を受け取れる
※基本の主契約は入院・手術の給付金のみで、通院の給付金については特約付帯となっている保険商品が多い
②生活習慣病保険:生活習慣病で所定の入院・手術をしたときに給付金を受け取れる保険。糖尿病を含む所定の生活習慣病に特化した保険
③その他:糖尿病の治療中・既往歴のある人でも加入できる緩和型医療保険※や、特定の薬物療法を受けたときに薬剤費用の給付金を受け取れる保険など。多様な商品がある
※緩和型医療保険については、別記事にて解説いたします。
最近は入院や手術時の保障だけではなく、通院時の給付金やまとまった一時金、薬物療法の保障等を受けられる保険が出てきていて、選択肢も多様化しています。さまざまある保険商品の中で、糖尿病治療に適した保険をどう選べばいいのでしょうか。自分にあった保険の選び方のポイントは、次項で詳しく解説していきます。
糖尿病に備える、自分にあった保険の選び方
糖尿病の治療に備えられる保険には、一般的な医療保険や生活習慣病保険、緩和型医療保険などがあるとお伝えしました。これらの保険の中で、ご自身に適したものを選ぶポイントは以下の5つです。
1. 現在の健康状態で入れる保険かどうか
ほとんどの保険には告知があるため、ご自身の健康状態によって加入できる保険は異なります。
持病も数年以内の病歴もなければ、加入できる保険の幅は広がります。一方で健康に不安がある場合は、加入できる保険が少なくなるので気をつけましょう。特に、糖尿病で治療歴があったり、健康診断で糖尿病予備軍の指摘を受けたりしている人は、一般的な医療保険や生活習慣病保険に加入できない可能性があります。また、たとえ加入できても、糖尿病に関する保障に条件が付くこともあります。
保険の加入の可否や条件の有無・内容は、保険会社に告知書を提出して審査を受けなければ確認できません。現在の健康状態に不安がある方は、保険会社や保険代理店で相談・確認してみるとよいでしょう。一般の保険が無理な場合は、緩和型医療保険を検討するのも一つの方法です。
2. 無理なく続けられる保険料か
保険は万が一のときのために加入するものですから、原則として「続けること」が何より大切です。
そのためには、家計にとって無理のない保険料である必要があります。
一般的に、保障が手厚い保険や、持病のある方でも検討できる緩和型医療保険は通常の医療保険より保険料が高く設定されています。保障の手厚さや、加入のしやすさを求めると、保険料の負担はどうしても高くなるものです。
どの保険種類を選ぶ場合でも、保険料が無理なく支払える・継続できる範囲であるか、家計と照らし合わせて検討しましょう。
3. 入院保障(給付金)の考え方
入院給付金は、入院した日数にあわせて給付金額が変動するものと、給付金をまとまった一時金で受け取れるタイプがあります。多くの場合は前者のため、ここでは入院日数にあわせて給付金額が変動するタイプについてお話しします。
入院給付金の金額は、日額5,000円~1万円で加入している人が多いです。仮に日額5,000円プランで30日入院すれば、合計15万円の給付金を受け取れることになります。
一般的な医療保険では入院給付金の支払日数は30日、60日などと上限が決まっています。長期入院に備えるには、支払日数を長くするとよいでしょう。
しかし、糖尿病患者の平均入院日数は33.3日。もちろん長期入院する方もいるでしょうが、最近は入院日数が短縮傾向にあります。本当に長期入院の保障が必要かは、よく考える必要があるでしょう。
<糖尿病患者の平均入院日数>
・平均入院日数:33.3日(男性26.7日/女性42.5日)
出典:厚生労働省「平成29年患者調査」より
ただし、治療に際し仕事を休んだり、家事・育児ができず代行サービスを頼んだりした場合には別の費用がかかります。さらに、通院時の交通費、差額ベッド代は公的医療保険制度の対象外です。これらの費用まで十分に保険でカバーしたい場合には、一般的な医療保険で入院給付金の日額を多めに設定するか、後述する一時金保障付きの生活習慣病保険を検討する方法もあります。
4. 手術保障(給付金)の考え方
手術給付金は、保険商品によって金額設定が異なります。
入院給付金の日額によって手術給付金の額が決まる商品もあれば、入院給付金の日額とは関係なく一律で決まっている商品もあります。また、日帰り手術の際は給付金額が少なくなる商品もあり、内容は保険会社によってさまざまです。
一般的には、手術給付金の額を手厚くすると、その分保険料も上がります。保障と保険のバランス、保険の対象となる手術の範囲をよく確認したうえで検討しましょう。
なお、保険の対象となる手術の範囲は、各保険会社の約款で定められています。
5. 通院保障(給付金)の考え方
通院給付金は、通院した日数に応じて受け取れるタイプが一般的です。
糖尿病は食事療法や薬物療法で通院する患者が多いため、通院給付金があれば日常的な治療費もカバーできます。短期入院の傾向が強くなっている現在、通院保障があれば糖尿病治療の備えとして安心です。ただし、一般的な医療保険の通院保障は、入院給付金の対象となる入院をして、退院後の通院を対象としています。入院をともなわない通院は保障されないものが多いのでご注意ください。
また、通院保障はすべての医療保険に付いているわけではありません。保険によっては、通院保障がない場合もあります。その場合通院保障は特約扱いとなり、保障を付けるとその分保険料が高くなります。
通院保障を付ける場合は、保険料と保障の兼ね合いをよく考え、無理のない契約プランになるようにしましょう。
一時金保障(給付金)の考え方
生活習慣病保険の中には、糖尿病で所定の状態になると、まとまった一時金を給付金として受け取れるものがあります。
まとまった給付金があれば治療費以外の費用に使いやすく、費用負担が気になる方には安心できる保障です。ただし、一時金を受け取るための「所定の状態」は、保険会社によって異なるため注意が必要です。
つまり、糖尿病と診断されただけですべての方に一時金が出るわけではありません。病状が進行して合併症が起きたり、所定の手術をしたりなど、糖尿病の中でも重篤な方に対し一時金が出るものもあります。一時金保障を付ける際は、必ず所定の状態を確認したうえで検討するようにしましょう。
まとめ
糖尿病は、自己管理によって病気の進行度合いをある程度コントロールできる病気です。
「糖尿病予備軍」の状態であれば日々の食事と運動習慣が重要なポイントになるため、まずは日々の生活習慣を見直すことから始めてください。
また、生活習慣を見直すとともに万が一の治療費負担に備えた保険選びもしておくと安心です。糖尿病は一般的な医療保険でも保障の対象になりますし、最近では治療中でも入れる保険やまとまった一時金を受け取れる保険も出てきています。ご紹介したポイントを参考に、ご家族と話し合って適切な保険を選んでおきましょう。
【次の記事】
・糖尿病にどう備える?糖尿病予防の健康習慣と事前の保険選び
・糖尿病になったら保険に入れない?糖尿病患者の保険の選択肢
【前の記事】
・糖尿病とは?きっかけ・症状・診断について